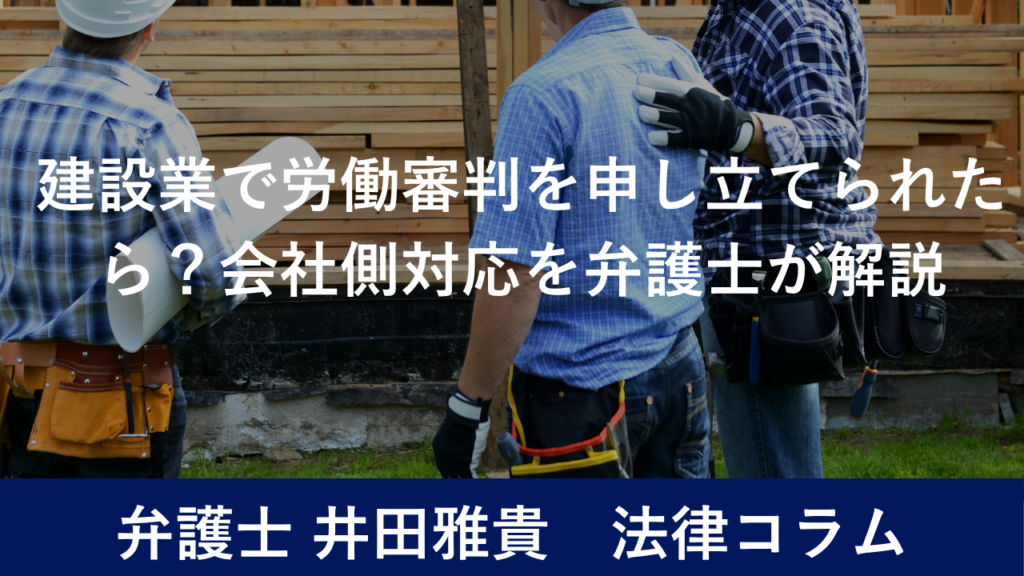
「先週、裁判所から労働審判の申立書が届きました。元作業員から未払残業代400万円を請求されています。現場の作業時間はきちんと管理していたつもりですが…」
大分県内の建設業者から、このような相談が寄せられることが増えています。2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されたことで、労働時間管理への意識が高まる一方、過去の労務管理の不備が労働審判という形で噴出しています。しかも労働審判は第1回期日まで原則40日以内という短期決戦。現場の証拠が散逸している中で、会社側が有効な反論を構築するのは極めて困難です。
本記事では、建設業で労働審判を申し立てられた際の初動対応から、建設業特有のチェックポイント、そして紛争後の体制整備まで、企業側労務問題の経験豊富な弁護士が実務的に解説します。
1. 建設業における労働紛争の傾向と労働審判の活用
建設業で労働審判が増加している背景
建設業界では近年、元作業員による労働審判の申立てが急増しています。その背景には、建設業特有の労務管理の難しさと、法改正による規制強化があります。
□ 2024年4月からの時間外労働上限規制の適用
建設業では長年、時間外労働の上限規制が適用猶予されていましたが、2024年4月からついに規制が適用されました。これにより、原則として月45時間・年360時間の上限が設けられ、違反すると罰則が科されます。この法改正を機に、過去の労働時間管理の実態が見直され、元作業員が「実は違法な長時間労働をさせられていた」と認識し、弁護士に相談するケースが増えています。
□ 残業代請求権の時効延長
2020年4月の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効が2年から3年に延長されました。これにより、請求額が単純に1.5倍に膨らみます。300万円だった請求が450万円になるわけです。建設業では長時間労働が常態化していたケースが多く、3年分を遡って計算すると、1人あたりの請求額が500万円を超えることも珍しくありません。
□ 日給月給制・現場払いの実態が不透明
建設業では日給月給制を採用している企業が多く、現場によって賃金が変動します。しかし、実際の労働時間や賃金計算の根拠が書面で残っておらず、「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。作業員側は「毎日12時間働いていた」と主張し、会社側は「休憩も含めて8時間程度だった」と反論しても、客観的証拠がなければ会社側の主張は認められません。
□ 多重下請構造による責任の所在の曖昧さ
建設現場では、元請・一次下請・二次下請という多重下請構造が一般的です。作業員がどの会社の指揮命令下にあったのか、誰が労働時間を管理していたのかが不明確で、労働審判でも争点になります。元請が「下請会社の作業員だから知らない」と主張しても、実態として元請の現場監督が直接指示を出していれば、元請にも責任が及ぶ可能性があります。
建設業における労働審判の特徴
建設業の労働審判には、他業種とは異なる独特の難しさがあります。
□ 現場作業記録の不備
建設現場では、出退勤時刻をタイムカードで記録している企業は少なく、作業日報も「本日の作業内容」を記すのみで、正確な労働時間は記録されていないことが大半です。このため、作業員側が「毎日朝7時から夜8時まで働いていた」と主張すると、会社側はそれを覆すだけの証拠を提出できず、不利な立場に立たされます。
□ 移動時間・待機時間の扱い
建設業特有の問題として、現場への移動時間、資材搬入待ちの時間、悪天候による作業中断時の待機時間などが労働時間に含まれるか否かが争われます。会社側は「自由時間だった」と主張しても、実態として指揮命令下にあった場合は労働時間と認定されます。
□ 安全教育・朝礼の時間
現場作業前の安全教育、朝礼、工具点検の時間が労働時間に含まれるかも争点です。会社側は「準備時間だから労働時間ではない」と考えがちですが、判例上、使用者の指揮命令下で行われる活動はすべて労働時間に含まれます。
大分県内でも、別府市や大分市の建設現場で働いていた元作業員からの労働審判が増えています。特に大規模な商業施設や公共工事の現場では、複数の下請業者が関与しており、責任の所在が不明確になりやすく、紛争のリスクが高まります。
2. 労働審判を申し立てられたら最初に確認すべきこと
申立書到着後、即日で実施すべき5つの対応
裁判所から労働審判の申立書が届いたら、当日中に以下の対応を開始してください。
□ 申立ての内容を正確に把握する
申立書には、請求の趣旨(未払残業代、解雇無効、慰謝料など)、請求の原因(なぜ請求するのか)、請求額の計算根拠が記載されています。建設業の場合、未払残業代請求が中心ですが、労働災害による安全配慮義務違反、パワハラによる慰謝料請求が併せて主張されることもあります。
□ 第1回期日までのスケジュールを逆算する
申立書には第1回期日の日時が記載されており、その1週間前までに答弁書を提出しなければなりません。つまり実質的な準備期間は30日前後しかありません。この短期間で、現場の作業記録、賃金台帳、雇用契約書などの証拠を収集し、法的に有効な反論を構築する必要があります。
□ 申立人の勤務実態を関係者から聴取する
申立人(元作業員)が実際にどのような働き方をしていたか、現場監督、職長、同僚作業員から事情を聴き取ります。「あいつは仕事が遅かった」といった感情的な情報ではなく、客観的事実を時系列で整理してください。特に以下の点を確認します。
- どの現場でいつからいつまで作業していたか
- 1日の標準的な作業時間(開始時刻、終了時刻、休憩時間)
- 移動時間、待機時間の扱い
- 賃金の支払方法(日給、月給、出来高払いなど)
□ 証拠書類を緊急で収集する
建設業の労働審判で必要となる証拠は多岐にわたります。以下の書類を優先的に収集してください。
- 就業規則、賃金規程
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 賃金台帳、給与明細
- 作業日報、出面帳(でづらちょう)
- 工事台帳、工程表
- 安全教育記録、朝礼記録
- タイムカード(あれば)
これらの証拠が存在しない、または散逸している場合、会社側は圧倒的に不利な状況に立たされます。
□ 労働問題に精通した弁護士に即日相談する
建設業の労働審判は、一般企業以上に専門的な知識が必要です。多重下請構造における責任の所在、移動時間や待機時間の労働時間該当性、安全配慮義務の内容など、判例法理の深い理解が求められます。「まずは社内で検討してから」と悠長に構えていると、あっという間に準備期間が過ぎてしまいます。
大分県内で建設業の労務問題に詳しい弁護士は限られています。申立書を受け取ったその日のうちに弁護士に連絡し、翌日には面談を設定すべきです。
絶対に避けるべき初動対応
□ 申立人や現場の同僚に直接接触する
「直接話し合って解決しよう」と元作業員に連絡を取ったり、同僚作業員に「裁判で会社側の味方をしてくれ」と依頼したりすることは、証人買収や圧力行為と受け取られ、会社側に極めて不利な心証を与えます。
□ 証拠を破棄・改ざんする
「作業日報に不利な記載がある」と気づいて書き換えたり、賃金台帳を改ざんしたりすれば、証拠隠滅として刑事責任を問われる危険があります。不利な証拠であっても、ありのまま提出することが、最終的には会社の信頼性を高めます。
□ 関係者で口裏を合わせる
「現場監督の証言を統一しよう」と口裏合わせをしても、労働審判委員会の尋問で必ず破綻します。事実を正直に報告することが重要です。
3. 建設業で特に重視すべきチェックポイント
建設業の労働審判では、以下の3点を重点的にチェックしてください。
(1) 作業時間・休憩記録
□ 作業開始時刻・終了時刻の立証
建設現場では、朝礼の時刻、作業開始の時刻、片付け・工具整理の時刻が曖昧になりがちです。作業員側は「朝7時から現場にいた」と主張し、会社側は「実際の作業は8時からだった」と反論しても、客観的証拠がなければ認められません。
有効な証拠:
- 朝礼の記録(日時、参加者)
- 現場出入りの記録(ゲート通過時刻、警備員の記録)
- 近隣住民への騒音配慮のための作業時間制限(「8時〜17時のみ作業可」など)
□ 休憩時間の実態
建設現場では、「昼休みは12時〜13時」と決まっていても、実際には作業が押して休憩を取れなかったり、資材搬入待ちで休憩が中断されたりします。休憩を取ったことの立証責任は会社側にあるため、以下の証拠を確保する必要があります。
- 作業日報に「12:00〜13:00 休憩」と明記されている
- 現場近くの飲食店やコンビニのレシート(昼食を買った証拠)
- 同僚作業員の証言
□ 移動時間の扱い
会社の事務所や資材置き場から現場までの移動時間が労働時間に含まれるかが争われます。判例上、「使用者の指示で特定の場所に集合し、そこから現場に移動する場合」は労働時間に含まれます。一方、「各自が自宅から直接現場に行く場合」は通勤時間であり、労働時間に含まれません。
□ 待機時間の扱い
雨天で作業が中断した場合、資材が届かず作業ができない場合などの待機時間が労働時間に含まれるかも争点です。会社側が「待機中は自由にしていい」と明示的に伝え、実際に作業員が現場を離れていた場合は労働時間に含まれませんが、「現場で待機していた」場合は労働時間と認定される可能性が高いです。
(2) 現場指揮命令系統
□ 誰が作業員に指示を出していたか
多重下請構造の建設現場では、元請の現場監督が下請会社の作業員に直接指示を出すことがあります。この場合、実質的な使用者は元請であり、元請が労働時間管理の責任を負う可能性があります。
確認すべき点:
- 作業指示書は誰が作成・交付していたか
- 日々の作業内容は誰が決定していたか
- 作業の進捗管理は誰が行っていたか
- 安全教育は誰が実施していたか
これらがすべて元請の現場監督によって行われていた場合、下請会社の作業員であっても、元請が労働審判の相手方となる可能性があります。
□ 請負契約か労働契約か
建設業では、一人親方や個人事業主との請負契約が多用されますが、実態が労働契約であれば、労働基準法が適用されます。判断基準は以下のとおりです。
請負契約と認められる要素:
- 作業方法や時間を自分で決定できる
- 材料や工具を自分で用意する
- 報酬が作業時間ではなく成果物に対して支払われる
労働契約と認められる要素:
- 会社の指示に従って作業する
- 会社の工具や資材を使用する
- 時間給や日給で報酬が支払われる
- 他の従業員と同じ作業をしている
実態が労働契約であれば、請負契約書を交わしていても労働基準法が適用され、残業代の支払義務が発生します。
(3) 安全教育記録
□ 安全教育の時間は労働時間か
建設現場では、作業開始前に安全教育や工具点検が義務付けられています。これらの時間が労働時間に含まれるか否かは、「使用者の指揮命令下で行われているか」で判断されます。判例上、使用者が実施を義務付けた安全教育は労働時間に含まれます。
会社側が「安全教育は労働時間に含まれない」と主張する場合、以下の点を立証する必要があります。
- 安全教育は任意参加であった
- 参加しなくても不利益はなかった
- 参加した場合は別途手当が支給されていた
これらの立証ができない場合、安全教育の時間は労働時間と認定され、その分の残業代を支払う必要があります。
□ 安全教育記録の整備
安全教育を実施した場合、その記録を保存しておくことが重要です。記録には以下の情報を含めてください。
- 実施日時
- 実施内容(墜落防止、重機操作、火災予防など)
- 参加者名
- 所要時間
これらの記録があれば、「安全教育の時間も含めて労働時間を計算していた」ことを立証できます。
4. 初期対応と弁護士との共同体制づくり
答弁書作成で重要なポイント
□ 請求原因事実への認否を明確にする
申立書の記載事項について、「認める」「否認する」「不知」を明確に示します。建設業の場合、「勤務していたこと」は認めても、「主張されている労働時間」は否認する、というように、事実を細かく分けて認否します。
□ 建設業特有の主張を構成する
「うちの業界では普通」という主張は通用しません。会社側の主張は、労働基準法や判例に基づいて法的に構成する必要があります。
例:
- 「移動時間は通勤時間であり労働時間に含まれない」→ 各自が自宅から直接現場に行っていたことを立証
- 「待機時間は自由時間だった」→ 待機中は現場を離れてもよいと指示していたことを立証
□ 証拠を効果的に提出する
作業日報、出面帳、賃金台帳などを提出する際には、「何を立証するための証拠か」を明確に示します。
弁護士との効果的な連携
□ 初回相談時の持参資料
弁護士との初回相談では、以下の資料を持参してください。
- 労働審判の申立書
- 申立人の雇用契約書、労働条件通知書
- 就業規則、賃金規程
- 直近3年分の賃金台帳、給与明細
- 作業日報、出面帳
- 工事台帳、工程表
- 安全教育記録
□ 現場の実態を詳細に説明する
弁護士は建設現場の実態を知らないため、現場監督や職長が詳細に説明する必要があります。特に以下の点を説明してください。
- 1日の標準的な作業の流れ
- 移動時間、休憩時間、待機時間の実態
- 賃金の計算方法
- 指揮命令系統
5. 建設業特有の初動ミスとその影響
よくある対応ミス
□ 「一人親方だから問題ない」という誤解
請負契約書を交わしているから労働基準法は適用されないと考えるのは誤りです。実態が労働契約であれば、労働基準法が適用されます。
□ 作業日報が存在しない
建設現場では作業日報が作成されていないことが多く、労働時間の立証ができません。この場合、作業員側の主張がそのまま認められる危険があります。
□ 下請会社に責任を押し付ける
元請が「下請会社の作業員だから知らない」と主張しても、実態として元請の現場監督が直接指示を出していれば、元請にも責任が及びます。
対応ミスがもたらすリスク
□ 高額な解決金の支払い
未払残業代に加えて、遅延損害金、付加金を支払うと、請求額の2倍以上の支払いを命じられることもあります。
□ 他の作業員への波及
1人の作業員の労働審判で敗訴すると、他の作業員も次々と請求してきます。建設業では同じような働き方をしている作業員が複数いるため、被害は一気に拡大します。
□ 建設業許可への影響
労働審判で敗訴した事実が建設業許可の更新時に問題視される可能性があります。また、公共工事の入札資格審査でも、労務管理の適正性が評価項目になっており、労働審判での敗訴は不利に働きます。
6. 紛争後の再発防止と体制整備
労働時間管理の徹底
□ タイムカード・ICカードの導入
建設現場でもタイムカードやICカードによる出退勤管理を導入してください。初期費用はかかりますが、労働審判のリスクを考えれば十分にペイします。
□ 作業日報の標準化
作業日報に、作業内容だけでなく、開始時刻、終了時刻、休憩時間を記載するよう標準化してください。
□ 安全教育記録の保存
安全教育を実施した際には、必ず記録を作成し、少なくとも3年間保存してください。
就業規則・契約書の整備
□ 就業規則の見直し
建設業に特化した就業規則を作成し、移動時間、待機時間、安全教育の時間の扱いを明確にしてください。
□ 雇用契約書の整備
日給月給制の場合、1日あたりの所定労働時間、休憩時間、賃金の計算方法を明記してください。
□ 請負契約書の精査
一人親方との請負契約が実態として労働契約になっていないか、弁護士による精査を受けてください。
7. 当事務所のサポート内容
大分県の建設業界に精通した迅速対応
リブラ法律事務所は、大分県内の建設業者の労務問題を扱ってきました。大分県下の建設現場では、公共工事から民間の商業施設まで多様なプロジェクトが進行しており、それぞれに労務管理の難しさがあります。当事務所は、大分県の建設業界の実情を深く理解し、実務的なアドバイスを提供します。
□ 労働審判申立て当日の相談対応
申立書を受け取ったその日にご連絡いただければ、即日または翌日に初回相談を設定します。第1回期日までの準備スケジュール、必要な証拠、反論の方向性を具体的にアドバイスします。
□ 第1回期日までの徹底サポート
証拠書類の収集・整理、関係者からの事情聴取、法的論点の分析、答弁書の作成、期日のシミュレーションまで、一貫してサポートします。
□ 労働審判期日への同行
弁護士が代理人として期日に同行し、労働審判委員会との交渉を行います。建設業特有の論点を的確に主張し、有利な調停案の成立を目指します。
紛争後の体制整備サポート(顧問契約の締結)
□ 就業規則・契約書の作成
建設業に特化した就業規則、雇用契約書、請負契約書を作成します。2024年4月からの時間外労働上限規制にも対応した内容にします。
□ 定期的な労務監査
年1回程度の労務監査を実施し、法令違反がないかをチェックします。問題が発見された場合、早期に是正策を提案します。
*顧問契約を締結いただくことで、日常的な労務相談、契約書のチェック、従業員とのトラブル対応など、幅広くサポートします。
弁護士: 井田雅貴
リブラ法律事務所代表。企業側の労務問題を専門とし、建設業、運送業、製造業など、労働時間管理が複雑な業種の労働審判を数多く手がけています。大分県内の企業を中心に、労務問題の予防から紛争解決まで幅広くサポートしています。
リブラ法律事務所
〒870-0049 大分県大分市中島中央2-2-2
電話: 097-538-7720
メールアドレス: lybra@triton.ocn.ne.jp
(メールをいただく際は貴社の商号や屋号のご記入をお願いします)
まとめ
建設業で労働審判を申し立てられた場合、初動対応が極めて重要です。40日以内という短期間で、作業記録や賃金台帳などの証拠を収集し、建設業特有の論点(移動時間、待機時間、安全教育、多重下請構造)について法的に有効な反論を構築しなければなりません。
対応が遅れれば、高額な解決金の支払い、他の作業員への波及、建設業許可への影響など、深刻なリスクに直面します。労働審判の申立書が届いたら、即日で労働問題に精通した弁護士に相談してください。リブラ法律事務所では、大分県内の建設業者を対象に、労働審判の初動対応から紛争後の体制整備まで、一貫したサービスを提供しています。まずはご相談ください。
Last Updated on 11月 18, 2025 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |





