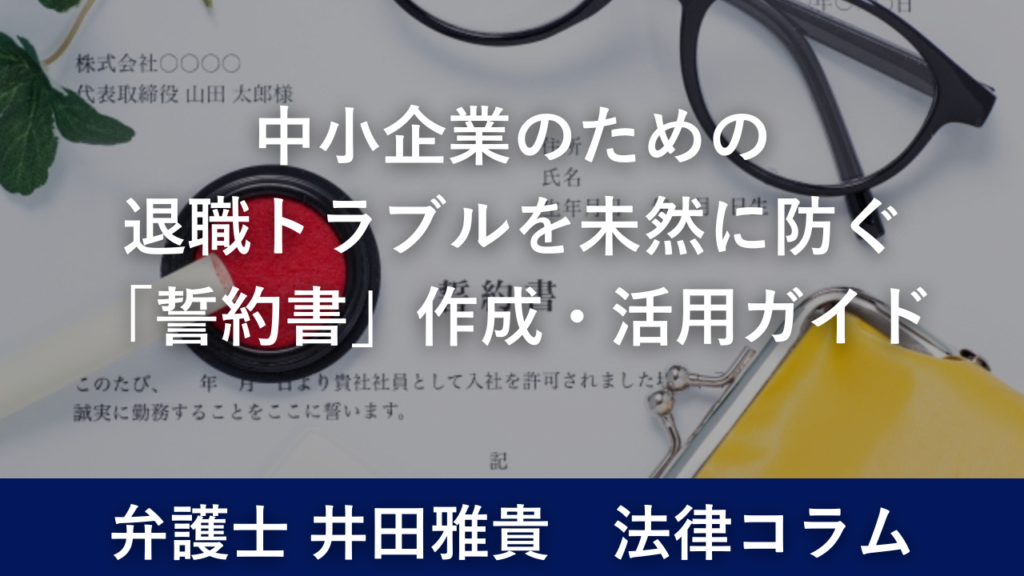
なぜ今、中小企業に「退職時誓約書」が必要なのか
「うちの会社は従業員との関係も良好だし、退職時のトラブルなんて無縁だよ」。そう思われている経営者の方もいらっしゃるでしょう。しかし、元従業員による顧客の引き抜き、社外秘情報の持ち出し、競合他社への転職によるノウハウ流出といった問題は、多くの中小企業が直面しうるリスクです。特に中小企業では、一人の従業員が持つ情報や顧客との関係性が事業に与える影響が大きく、一度トラブルが発生すると、そのダメージは計り知れません。
本記事では、退職時誓約書を、会社を守るための武器として活用するための実践的な知識を解説します。法的に有効な誓約書の作り方から、トラブル発生時の対応策まで、中小企業の経営者にとって必要な情報をお届けします。
1. 退職時誓約書とは何か?その目的と重要性
退職時誓約書とは、従業員が退職する際に、会社と従業員の間で、退職後の一定の義務(秘密情報を漏らさない、競合会社に転職しないなど)について約束する法的文書です。
主な目的は以下の通りです。
- 企業の機密情報・顧客情報・技術ノウハウの保護:これらの外部流出や不正利用を防ぎます。
- 不正競争の防止:元従業員による顧客引き抜きや競合事業立ち上げを抑止します。
- 企業ブランドや信用の維持:元従業員による会社への誹謗中傷を防ぎます。
中小企業において退職時誓約書が特に重要なのは、以下の理由からです:
- 人材の流動性が高まっており、従業員の転職は日常的になっている。
- 大企業に比べて情報管理体制が整っていないことが多い。
- 一人の退職者が事業に与える影響が大きく、顧客や重要情報の流出リスクが高い。
2. 退職時誓約書の法的効力と有効性
従業員との間で合意された誓約書は、原則として法的効力を持ちます。ただし、どんな内容でも有効というわけではありません。
有効な誓約書の条件
- 内容の合理性:退職者に課す義務が、会社の正当な利益を守るために必要な範囲内であること。
- 従業員の自由とのバランス:憲法で保障されている職業選択の自由などを不当に侵害していないこと。
- 代償措置の有無:特に競業避止義務を課す場合、その見返りとなる金銭補償があると有効性が認められやすくなります。
無効となるリスクのある誓約書
- 公序良俗に反する内容:社会の一般的な秩序や道徳観念に反する極端な内容。
- 強迫や錯誤による署名:従業員が脅されたり、騙されたりして署名した場合。
- 内容が曖昧すぎる:禁止事項や義務が具体的に書かれておらず、解釈の余地が大きすぎる場合。
- 一方的に不利益な内容:会社側の利益のみを追求し、従業員の権利を不当に制限する内容。
裁判例から見る無効リスク
実際に裁判で誓約書の一部が無効と判断された例
- 退職後6ヶ月間の競業避止義務を定めた誓約書が無効と判断された事例
- 退職後3年間の秘密保持義務(広範な情報を含む)を定めた誓約書が無効と判断された事例
安易な雛形の利用は避け、自社の実情に合わせて専門家と相談しながら作成することが重要です。
3. 退職時誓約書に含めるべき主な内容
3-1. 秘密保持義務
業務上知り得た会社の機密情報を退職後に漏洩したり不正利用したりしないことを約束させる条項です。
- 保護すべき「秘密情報」の範囲を具体的に定義する: 「顧客リスト、仕入先リスト、製品原価情報、製造ノウハウ、技術情報」など具体的に例示します。
- 禁止行為を明確に: 開示、漏洩、目的外使用、複製、持ち出しなどを具体的に列挙します。
- 義務の存続期間: 情報の性質に応じて「退職後○年間」など合理的な期間を設定します。
秘密保持義務条項の例
「乙(退職者)は、甲(会社)の業務を通じて知り得た以下の情報(以下「秘密情報」という)について、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に開示・漏洩せず、また自己もしくは第三者のために使用しないことを誓約します。秘密情報には、顧客情報、技術情報、財務情報、人事情報、その他甲が秘密として管理する一切の情報を含みます。本義務は、乙の退職後も○年間存続するものとします。」
3-2. 競業避止義務
従業員の競合他社への転職や同種事業の開業を制限する条項です。有効性が厳しく判断されるため注意が必要です。
- 制限する期間: 6ヶ月~1年程度が現実的です。長すぎると無効リスクが高まります。
- 制限する地域: 会社の事業エリアに応じて具体的に設定します。
- 制限する業務範囲: 退職者が担当していた業務を具体的に特定します。
- 代償措置: 競業避止義務への見返りとして、退職金の上乗せなど金銭的補償を設けると有効性が高まります。
競業避止義務条項の例
「乙は、甲を退職後6ヶ月間、○○県において、甲と競合する事業(具体的に:○○事業)を自ら営み、または競合他社に就職しないことを誓約します。甲は、本義務の代償として、乙に対し金○○円を支払うものとします。」
代償措置がない場合、無効となる可能性が高まります。期間、地域、業務範囲は最小限に限定しましょう。
3-3. 顧客引き抜き禁止条項
退職者による顧客や従業員の引き抜きを防ぐための条項です。
- 禁止する行為: 顧客への営業勧誘、従業員への転職勧誘などを具体的に記載します。
- 対象範囲: 「在職中に担当した顧客」「退職前○年間に取引のあった顧客」など対象を特定します。
- 禁止期間: 1~2年程度の合理的な期間を設定します。
顧客引き抜き禁止条項の例
「乙は、甲を退職後1年間、乙が甲在職中に担当した顧客に対し、甲の事業と競合する商品・サービスを提供するための営業活動を行わないこと、また、甲の従業員に対し、甲からの退職を勧誘する行為を行わないことを誓約します。」
3-4. その他の重要な条項
- 貸与物の返還義務: パソコン、携帯電話、社員証、資料、データなどの返還を約束させます。
- 個人所有機器のデータ削除: 私物PCやスマートフォンに保存された業務データの削除を確認します。
- SNS等での誹謗中傷禁止: 退職後にSNSなどで会社の信用を毀損する情報発信をしないよう約束させます。
- 損害賠償条項: 誓約違反時の損害賠償責任について明記します。
4. 効果的な誓約書作成のステップ
4-1. 準備フェーズ
- 自社が守るべきものを明確にする: 機密情報、顧客基盤、技術的優位性など、具体的にリストアップします。
- 従業員の立場に応じた内容を検討する: 役職や職種によって、アクセスできる情報や責任範囲が異なります。全員に同じ内容は適切でない場合があります。
- 就業規則との整合性を確認する: 就業規則に退職後の義務に関する基本的な定めがあるか確認します。
4-2. 誓約書作成・締結時の重要ポイント
- 従業員への丁寧な説明: 誓約書の内容や必要性を説明し、理解と納得を得ることが重要です。
- 署名のタイミング: 退職日または退職直前が一般的です。
- 誓約書の保管: 2部作成し、会社と本人が各1部を保管します。
- 雛形の安易な利用は危険: インターネット上の雛形をそのまま使うのではなく、自社の状況に合わせてカスタマイズしましょう。
誓約書作成の5つのポイント
- 保護すべき情報や禁止行為を具体的に記載する
- 期間・地域・範囲は合理的な限度内に設定する
- 競業避止義務には可能な限り代償措置を設ける
- 従業員と丁寧に対話し、理解を得てから署名してもらう
- 専門家(弁護士)に相談して内容をチェックしてもらう
5. 誓約書をめぐるトラブル対応
5-1. 従業員が署名を拒否した場合
- 理由の確認と対話: なぜ署名を拒否するのか理由をヒアリングし、誓約書の必要性を丁寧に説明します。
- 内容の調整: 従業員の懸念点に配慮し、会社が許容できる範囲で内容を調整することも検討します。
- 高圧的な対応は避ける: 「署名しないと退職金を減額する」といった対応は、就業規則等に明確な根拠がない限り問題です。
- 代替措置: 署名が得られない場合も、退職面談で秘密保持等について口頭で説明し、議事録に残しておくことが有効です。
5-2. 誓約違反が発覚した場合の対応
- 事実確認と証拠収集: 本当に違反があったのか、客観的な証拠を収集します。
- 違反者への警告: 違反が確認できた場合、まずは内容証明郵便などで警告し、違反行為の中止を求めます。
- 法的措置の検討: 警告しても是正されない場合は、弁護士と相談の上、差止請求や損害賠償請求などの法的措置を検討します。
5-3. トラブル予防策
- 入社時の秘密保持契約: 入社時から秘密保持義務について合意しておきましょう。
- 就業規則の整備: 情報管理規定を明確にし、全従業員に周知徹底します。
- 定期的な研修: 情報セキュリティに関する研修を定期的に実施します。
- 良好な労使関係: 日頃から信頼関係を構築し、「辞めるから関係ない」と思わせないような職場環境を作ることも重要です。
6. 具体的な事例から学ぶ
事例1:技術情報の流出を防いだA社
独自の技術力が強みのA社では、核心技術を持つエンジニアの退職時に、秘密保持義務と1年間の競業避止義務(代償措置あり)を含む誓約書を締結。その結果、技術情報の流出を防ぎ、競争力を維持できました。
事例2:顧客引き抜きを防止したB社
B社では、過去に営業担当者の退職によって顧客を失う経験をしたことから、退職時誓約書に2年間の顧客引き抜き禁止条項を導入。次の退職者発生時に誓約書に基づいて警告したところ、大規模な顧客流出を防ぐことができました。
まとめ:退職時誓約書で会社を守るために
最重要ポイント
- 退職時誓約書は、情報漏洩や顧客引き抜きから中小企業を守るための重要なツールです。
- 法的効力のある誓約書を作成するには、具体性、合理性、バランスが重要です。
- 従業員との丁寧な対話と、日頃からの情報管理体制の整備が、退職トラブル予防の鍵となります。
- 専門家(弁護士)の助言を得ながら、自社に最適な誓約書を作成しましょう。
退職時誓約書は、単なる形式的な書類ではなく、会社の貴重な資産を守るための実効性のあるツールとなり得ます。本記事を参考に、自社の状況に合わせた誓約書の整備と、退職トラブルの予防策を考えてみてください。大切な会社を守るための一歩を、今日から踏み出しましょう。
7. 退職時の誓約書と就業規則の作成・変更は専門家との連携が不可欠
ここまでお読みいただき、誓約書の重要性はご理解いただけたかと思います。しかし、いざ自社で作成するとなると、法的な妥当性の判断など、不安な点も多いのではないでしょうか。その際は、まずは顧問弁護士に相談してみましょう。もし顧問弁護士がいない場合は、中小企業の労務問題に強い弁護士を探すのが第一歩です。また、初回相談が無料の事務所もあります。
なぜ弁護士への相談が必要なのか
1. 法的有効性の確保 雛形をそのまま使用したり、インターネット上の情報だけで作成したりした誓約書では、自社の事例にフィットせず法的効力を否定されることがあります。弁護士に相談すれば、最新の法改正や裁判例を踏まえて、確実に効力を発揮する文書を作成できます。
2. 自社の実情に合わせたカスタマイズ 業種、規模、取引形態、従業員構成など、会社によって守るべきものは異なります。弁護士は自社の事業特性を理解した上で、本当に必要な保護を実現する誓約書を設計します。
3. 従業員との信頼関係の維持 過度に厳しい条項は従業員の反発を招くだけでなく、法的にも無効となるリスクがあります。弁護士は会社の利益保護と従業員の権利のバランスを考慮した、合理的な内容の誓約書作成をサポートします。
4. 就業規則との整合性確保 誓約書の内容と就業規則が矛盾していると、どちらも効力が弱まることがあります。弁護士は就業規則と誓約書の整合性を確保し、総合的な法的防衛体制を構築します。
5. トラブル発生時の迅速な対応 万が一、誓約書違反が疑われる状況が生じた場合、初動対応が極めて重要です。日頃から相談している弁護士であれば、会社の状況を理解した上で、迅速かつ的確なアドバイスが得られます。
コストパフォーマンスの高い投資
弁護士への相談料は決して安くはありませんが、重要な従業員の退職によって核心的な顧客や技術情報が流出した場合のダメージと比較すれば、極めて合理的な「予防投資」と言えます。適切な誓約書があれば、トラブルを未然に防止できる可能性も高まります。
特に中小企業の場合、一人の退職者による顧客の引き抜きや情報の持ち出しが、事業存続に関わる深刻な問題に発展することもあります。適切な誓約書を整備することは、単なる守りではありません。安心して従業員に権限を委譲し、事業成長を加速させるための『攻めの経営基盤』づくりともいえるのです。
Last Updated on 7月 25, 2025 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |





