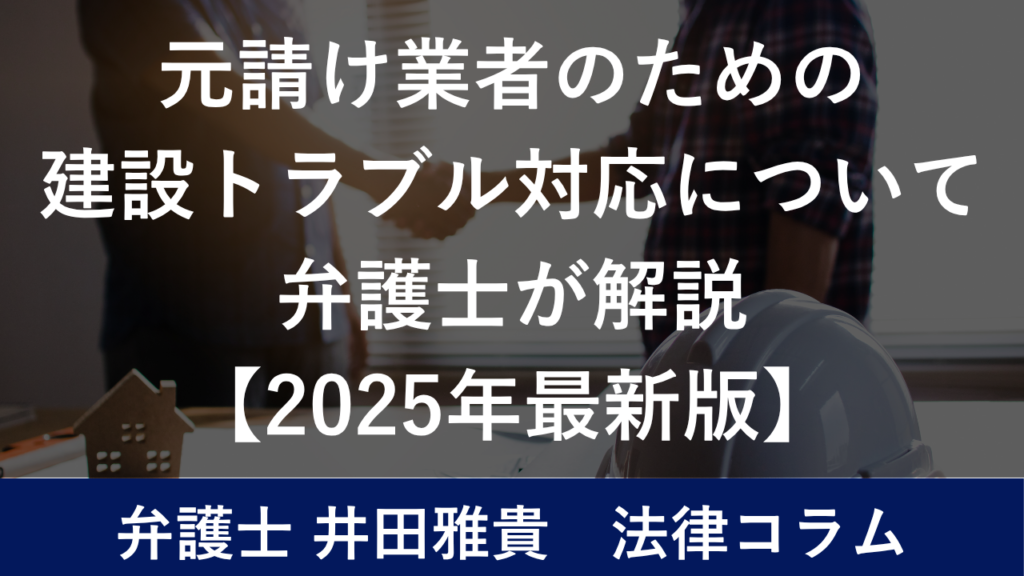
建設業界は今、大きな変革期を迎えています。2024年問題に代表される働き方改革、DX(デジタルトランスフォーメーション)の波、そして人材不足という三重苦の中で、中小規模の元請け業者には従来以上に高度なリスク管理が求められています。
建設業界特有の複雑な多重請負構造の中で、元請け業者として事業を継続していくためには、法的リスクを適切に把握し、事前に対策を講じることが不可欠です。本記事では、建設業に精通した弁護士の視点から、元請け業者が直面しやすいトラブルの実態と、その効果的な対応策について詳しく解説します。
1. 元請け業者が直面しやすいトラブルとは
1-1. 工事代金をめぐるトラブル
建設業界において最も頻繁に発生するのが、工事代金に関するトラブルです。特に元請け業者として注意すべき点は多岐にわたります。
施主からの代金未払い・支払い遅延
工事完成後に施主が代金を支払わない、または支払いを大幅に遅延させるケースが増加しています。2025年現在、建設資材の高騰や人件費の上昇により、中小建設会社のキャッシュフローは非常に厳しい状況にあります。このような状況下で代金回収ができないと、資金繰りに深刻な影響を与えかねません。
施主側の言い分として多いのは、「工事の品質に問題がある」「完成時期が遅れた」「追加工事の説明を受けていない」といったものです。しかし、これらの主張の多くは、契約書の内容が曖昧であったり、変更工事の記録が不十分であったりすることに起因しています。
追加変更工事の代金トラブル
建設工事では、施工過程で追加や変更が発生することは珍しくありません。しかし、「口約束」で工事を進めてしまい、後から代金を請求した際に「そんな話は聞いていない」と言われるケースが後を絶ちません。
建設業法では、軽微な変更工事を除き、追加変更工事についても書面による契約の締結が義務付けられています。この規定を軽視すると、代金回収ができないだけでなく、建設業法違反として行政処分の対象となるリスクもあります。
下請代金の支払いトラブル
元請け業者は、下請業者への支払い義務を負っています。しかし、施主からの入金が遅れた場合でも、下請代金の支払期日は変更できません。建設業法では、下請代金の支払期日について厳格な規定が設けられており、違反すると監督処分や営業停止処分の対象となります。
また、下請業者への不当な代金減額も重大な問題です。「品質が悪い」「工期に遅れた」などの理由で一方的に代金を減額することは、下請代金支払遅延等防止法(「取適法」と呼びます。)違反や建設業法違反に該当する可能性があります。
1-2. 契約不適合責任(瑕疵担保責任)に関するトラブル
施工不良による損害賠償請求
建築物の雨漏り、ひび割れ、傾き、断熱性能の不足など、施工不良による問題は元請け業者にとって重大なリスクです。民法の契約不適合責任により、施主から修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、さらには契約解除を求められる可能性があります。
特に注意すべきは、元請け業者の責任範囲の広さです。下請業者の施工ミスであっても、元請け業者は施主に対して責任を負わなければなりません。その後、下請業者に対して求償することになりますが、下請業者の資力が不足している場合は、結果的に元請け業者が全損失を被ることになります。
設計変更に伴う責任問題
工事の進行中に設計変更が必要となった場合、その責任の所在を明確にしておかないと後々大きなトラブルになります。地盤調査の結果、当初の設計では不十分であることが判明した場合、誰がその追加費用を負担するのか、工期の遅延責任はどこにあるのかなど、複雑な問題が発生します。
1-3. 労務管理上のトラブル
2024年問題への対応不足
2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されており、2025年現在も多くの建設会社がこの問題に苦慮しています。従来の長時間労働に依存した働き方を改善できずにいると、労働基準法違反のリスクが高まります。
元請け業者として特に注意すべきは、工期設定の責任です。無理な工期を設定し、それが下請業者の長時間労働を招いた場合、元請け業者も責任を問われる可能性があります。
労働災害に関する責任
建設現場では、元請け業者は元方事業者として、下請業者の労働者も含めた安全配慮義務を負っています。労働災害が発生した場合、被災者が下請業者の従業員であっても、元請け業者の安全配慮義務違反が問われることがあります。
また、労働安全衛生法に基づく各種義務(統括安全衛生責任者の選任、安全衛生協議会の設置等)を怠ると、行政処分の対象となるだけでなく、民事責任も問われる可能性があります。
偽装請負の問題
人手不足が深刻化する中、実態としては労働者派遣に該当するにもかかわらず、請負契約の形式を取る「偽装請負」の問題が増加しています。労働者派遣法や職業安定法違反として刑事責任を問われるリスクがあるほか、労働災害が発生した場合の責任関係も複雑になります。
1-4. 近隣住民とのトラブル
騒音・振動に関するクレーム
建設工事に伴う騒音や振動は、近隣住民との間で深刻なトラブルに発展することがあります。特に住宅密集地での工事では、工事時間の制限、作業方法の変更、防音対策の実施など、様々な対応が求められます。
近隣住民からの抗議が激化すると、工事の中断を余儀なくされ、工期の大幅な遅延や追加費用の発生につながります。最悪の場合、損害賠償請求や工事差し止め訴訟に発展することもあります。
環境影響に関する問題
大規模な建設工事では、環境アセスメントや各種許認可の取得が必要です。これらの手続きを適切に行わずに工事を開始すると、行政指導や工事停止命令を受けるリスクがあります。また、環境破壊や景観破壊を理由とした住民訴訟のリスクも存在します。
1-5. 建設業許可・コンプライアンス関連のトラブル
建設業法違反のリスク
建設業法は建設業者に対して厳格な規制を設けており、違反すると営業停止処分や許可取消処分などの重い行政処分を受ける可能性があります。主な違反事例としては、以下のようなものがあります。
- 無許可営業(許可業種外の工事受注)
- 契約書面の不備・未作成
- 下請代金の支払遅延
- 一括下請負の禁止違反
- 技術者の専任義務違反
独占禁止法・取適法違反のリスク
元請け業者として下請業者との取引を行う際は、独占禁止法や取適法の規制も受けます。優越的地位の濫用として問題となりやすいのは、以下のような行為です。
- 下請代金の不当な減額
- 不当な返品・やり直し要求
- 不当な経済上の利益提供要求
- 支払遅延
これらの行為は、公正取引委員会による調査の対象となり、課徴金や損害賠償責任を負うリスクがあります。
2. 元請け業者がとるべき法的リスク対策
2-1. 契約書の整備と管理
工事請負契約書の重要条項
元請け業者として最も重要な法的リスク対策は、適切な契約書の作成と管理です。建設業法に準拠した契約書を作成することはもちろん、以下の点についても詳細に規定しておく必要があります。
工事内容の明確化
工事の範囲、仕様、使用材料、施工方法などを図面と照らし合わせながら詳細に記載します。曖昧な表現は後々のトラブルの原因となるため、可能な限り具体的に記述することが重要です。
代金・支払条件の明確化
工事代金の総額、出来高に応じた支払スケジュール、支払方法、遅延損害金などを明確に定めます。また、追加変更工事が発生した場合の代金算定方法についても予め規定しておくことが重要です。
工期・納期の設定
工期については、天候不良、資材調達の遅延、設計変更などのリスク要因を考慮した現実的な設定が必要です。また、工期遅延が発生した場合の責任関係や損害の負担についても明確に定めておきます。
契約不適合責任の制限
施工後に発見される可能性のある不具合に対する責任範囲を適切に制限することも重要です。ただし、消費者契約の場合は消費者契約法の制約があるため、法的に有効な制限条項を設ける必要があります。
下請契約書の整備
下請業者との契約においても、建設業法第19条に基づく適切な契約書の作成が義務付けられています。特に以下の点に注意が必要です。
責任範囲の明確化
各下請業者の施工範囲と責任範囲を明確に区分し、問題が発生した場合の責任関係を予め整理しておきます。複数の下請業者が関与する工事では、責任の境界が曖昧になりがちですが、これを明確にしておくことで後々のトラブルを防止できます。
品質管理基準の設定
下請業者に求める品質水準を具体的に示し、検査方法や不適合品の取り扱いについても詳細に規定します。品質管理基準を明確にすることで、施主からのクレームリスクを軽減できます。
2-2. リスク管理体制の構築
工事管理システムの導入
2025年現在、建設業界でもDXの導入が急速に進んでいます。工事管理システムを導入することで、以下のようなリスク管理の効率化が可能です。
- 工程管理の可視化による工期遅延リスクの早期発見
- 品質管理記録のデジタル化による証拠保全
- 下請業者との情報共有の円滑化
- コンプライアンスチェック機能による法令違反の防止
現場監督体制の強化
建設業法では、工事現場における技術者の専任配置が義務付けられています。これを確実に履行するとともに、現場監督者の権限と責任を明確にし、適切な工事管理を行う体制を構築する必要があります。
特に重要なのは、以下の点です。
安全管理体制の確立
労働安全衛生法に基づく安全管理体制を構築し、定期的な安全教育や安全点検を実施します。労働災害の発生は、被災者への損害賠償責任だけでなく、企業の社会的信用失墜にもつながります。
品質管理体制の強化
各工程における品質検査を確実に実施し、記録を残します。問題が発見された場合は速やかに改善措置を講じ、その記録も保管しておくことで、後々のクレーム対応に活用できます。
2-3. コンプライアンス体制の整備
建設業法遵守のためのチェック体制
建設業法違反は営業停止や許可取消といった重大な行政処分につながるため、法令遵守のためのチェック体制を整備することが不可欠です。
許可業種の確認
請け負う工事が自社の建設業許可の範囲内であることを、契約前に必ず確認します。許可を受けていない業種の工事を請け負うことは、無許可営業として重大な法律違反となります。
一括下請負の禁止
建設業法では、工事の全部を一括して下請けに出すことを禁止しています。元請け業者として実質的な関与を行わず、単なる取次ぎ業務となってしまわないよう注意が必要です。
技術者の適正配置
工事現場には、適切な資格を持つ技術者を専任で配置する必要があります。複数現場の兼務や名義貸しは厳格に禁止されており、違反すると重い処分を受けることになります。
労働法令の遵守
2024年問題以降、建設業界でも労働時間管理がより厳格になっています。元請け業者として以下の点に注意が必要です。
労働時間の適正管理
自社従業員の労働時間管理はもちろん、下請業者の労働者についても、元方事業者として適正な労働時間での作業を確保する責任があります。
安全配慮義務の履行
労働契約法第5条に基づく安全配慮義務は、下請業者の労働者に対しても及ぶ場合があります。適切な安全措置を講じず、労働災害が発生した場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。
2-4. 保険・金融的リスク対策
工事保険の活用
建設工事には様々なリスクが伴うため、適切な保険への加入が重要です。
工事保険(建設工事保険)
工事中の火災、爆発、台風等による工事目的物の損害をカバーします。特に大規模工事では、損害額が億単位になることもあるため、十分な補償額の設定が必要です。
第三者賠償責任保険
工事に起因して第三者に損害を与えた場合の賠償責任をカバーします。近隣建物への損傷、通行人への被害など、建設工事特有のリスクに対応できます。
生産物賠償責任保険(PL保険)
完成した建築物の欠陥により第三者に損害を与えた場合の賠償責任をカバーします。特に住宅建設では、入居後に発見される不具合に対する備えとして重要です。
財務管理の強化
キャッシュフロー管理
建設業は資金の先出しが多い業界特性があるため、綿密なキャッシュフロー管理が不可欠です。工事代金の回収予定と下請代金の支払義務を正確に把握し、資金ショートを防ぐ必要があります。
与信管理の徹底
新規取引先との契約前には、必ず与信調査を実施します。特に個人施主の場合は、住宅ローンの承認状況や自己資金の確保状況を確認することが重要です。
3. 弁護士に相談すべきタイミングと内容
3-1. 予防法務としての相談タイミング
契約締結前の法務チェック
「トラブルが発生してから弁護士に相談する」という従来の考え方では、既に手遅れとなっているケースが多いのが実情です。真にリスクを回避するためには、予防法務の観点から、以下のタイミングで弁護士への相談を検討すべきです。
新規取引先との契約前
特に大型案件や新しい取引先との契約については、契約条件の法的妥当性を事前にチェックすることが重要です。不利な条件での契約締結を避けることで、将来のトラブルリスクを大幅に軽減できます。
契約書雛形の作成・見直し
自社で使用している契約書雛形について、法改正や判例の動向を踏まえた定期的な見直しが必要です。古い雛形をそのまま使用していると、現在の法令に適合しない条項が含まれている可能性があります。
社内規程の整備
就業規則の見直し
2024年問題への対応として、労働時間管理に関する規定を適切に整備する必要があります。また、建設業特有の労働形態(直行直帰、宿泊を伴う工事等)に対応した規定の整備も重要です。
安全管理規程の策定
労働安全衛生法に基づく安全管理体制を社内規程として明文化し、責任体制を明確にします。これにより、労働災害発生時の責任軽減効果も期待できます。
3-2. トラブル発生時の緊急対応
初期対応の重要性
トラブルが発生した場合、初期対応の適切性がその後の解決に大きく影響します。感情的な対応や場当たり的な判断は、事態をより悪化させる可能性があります。
証拠保全の実施
トラブルの内容に関係なく、まずは客観的事実の把握と証拠保全が最優先です。現場写真、図面、契約書、やり取りの記録など、関連する全ての資料を整理・保管します。
相手方との交渉前の法的分析
相手方との直接交渉を行う前に、法的な責任関係を正確に分析することが重要です。感情的な対応や根拠のない主張は、かえって問題を複雑化させる原因となります。
緊急性の高いケース
以下のような状況では、可能な限り迅速に弁護士への相談を行うべきです。
行政機関からの指導・処分通知
国土交通省や都道府県から建設業法違反に関する指導や処分の通知を受けた場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応策を検討する必要があります。行政処分は営業活動に直接影響するため、迅速な対応が求められます。
労働災害の発生
現場で労働災害が発生した場合は、被災者への対応と併せて、法的責任の分析と今後の対応策について弁護士と協議する必要があります。初期対応を誤ると、損害賠償額が大幅に増加するリスクがあります。
工事差し止め要求
近隣住民や行政機関から工事の差し止めを要求された場合は、法的根拠の有無を速やかに分析し、適切な対応を検討する必要があります。工事の長期中断は、元請け業者にとって致命的な損失となりかねません。
3-3. 具体的な相談内容と準備すべき資料
代金回収に関する相談
相談内容
- 未払い代金の回収方法
- 回収可能性の法的評価
- 内容証明郵便の作成
- 仮差押え等の保全措置の検討
- 訴訟提起の判断
準備すべき資料
- 工事請負契約書
- 工事代金の請求書・見積書
- 工事完成確認書
- 追加変更工事に関する資料
- 相手方との交渉記録
契約不適合責任に関する相談
相談内容
- 施主からのクレームの法的妥当性
- 修補義務の範囲と方法
- 損害賠償責任の有無・範囲
- 下請業者への求償の可能性
- 保険適用の検討
準備すべき資料
- 設計図面・施工図面
- 施工記録・検査記録
- クレーム内容の詳細
- 現場写真・動画
- 専門家による調査報告書
労務問題に関する相談
相談内容
- 労働時間管理の適正化
- 安全管理体制の見直し
- 労働災害発生時の対応
- 未払い残業代請求への対応
- 偽装請負疑義への対応
準備すべき資料
- 就業規則・労働契約書
- 勤怠管理記録
- 安全管理記録
- 労働災害報告書
- 下請契約書
4. 建設業に強い弁護士を選ぶポイント
4-1. 専門性と実績の確認
建設業法への精通度
建設業に関わる法律問題は、建設業法、民法、労働法、労働安全衛生法など、複数の法分野にまたがる複雑な問題です。一般的な企業法務の経験だけでは対応が困難な場合が多いため、建設業法に精通した弁護士を選ぶことが重要です。
確認すべきポイント
- 建設業法違反事件の取扱実績
- 行政処分に対する対応経験
- 建設業許可申請・更新の支援実績
- 業界特有の商慣行への理解度
訴訟・紛争解決の実績
建設業に関わる紛争は、一般的な商事紛争と比べて技術的・専門的な争点が多く含まれます。そのため、建設業に関する訴訟や調停の豊富な経験を持つ弁護士を選ぶことが重要です。
実績確認の方法
- 建設業関連の解決事例の公表状況
- 建設業界向けのセミナー・研修の実施実績
- 建設業界団体との関係性
- 専門誌への寄稿や著作物の有無
4-2. 対応体制とアクセスの良さ
緊急対応体制
建設業では、現場での事故や急なトラブルが発生することがあります。このような緊急事態に迅速に対応できる弁護士事務所を選ぶことが重要です。
確認すべき体制
- 平日夜間・休日の連絡体制
- 現場への出張対応の可否
- チーム制による対応の充実度
- オンライン相談の対応状況
アクセス・立地条件
定期的な相談や打ち合わせを考慮すると、事務所の立地も重要な選択要素です。特に地域密着型の中小建設会社の場合、地元の法律事務所の方が、地域の商慣行や行政機関の対応に精通している場合があります。
4-3. 費用体系の透明性
明確な料金体系
法律相談や訴訟対応にかかる費用について、明確で分かりやすい料金体系を提示している弁護士事務所を選ぶことが重要です。特に中小企業にとって、予想外の高額請求は経営に深刻な影響を与える可能性があります。
確認すべき費用項目
- 初回相談料の有無
- 顧問契約の料金体系
- 訴訟事件の着手金・報酬金
- 出張費・実費の扱い
- 成功報酬制の適用可否
コストパフォーマンスの評価
単純に料金の安さだけでなく、提供されるサービスの質と料金のバランスを総合的に評価することが重要です。経験豊富な弁護士による適切な初期対応は、結果的にトラブル解決にかかる総コストを削減する効果があります。
4-4. 技術的専門知識の有無
建築・土木技術への理解
建設業に関わる法律問題の多くは、技術的な争点を含んでいます。そのため、弁護士自身が建築や土木に関する基本的な知識を持っているか、または信頼できる技術専門家とのネットワークを持っているかが重要な選択要素となります。
重要な専門分野
- 構造設計・施工技術
- 建築基準法・関連法令
- 工事積算・原価管理
- 品質管理・検査技術
- 安全管理技術
専門家ネットワークの活用
複雑な技術的争点がある場合、弁護士単独での対応には限界があります。一級建築士、構造設計士、施工管理技士などの技術専門家と連携できる体制を持つ弁護士事務所を選ぶことで、より適切な解決策を期待できます。
5. 弁護士への相談で得られる具体的なメリット
5-1. リスクの早期発見と予防
法的リスクの可視化
弁護士による定期的な法務チェックにより、潜在的なリスクを早期に発見できます。これにより、問題が深刻化する前に適切な対策を講じることが可能になります。
具体的な効果
- 契約条件の不備による損失回避
- 法令違反リスクの事前排除
- 取引先の与信リスクの早期発見
- 労務管理上の問題の予防
業界動向・法改正への適応
建設業を取り巻く法的環境は常に変化しています。弁護士からの情報提供により、法改正や新しい規制への適応を円滑に進めることができます。
2025年現在の重要トピック
- DX推進に伴う新しい法的課題
- 働き方改革関連法の完全施行への対応
- 環境規制の強化(カーボンニュートラル対応)
- 外国人労働者の受入れ拡大に伴う法的問題
5-2. トラブル解決の効率化
専門的知見による適切な判断
建設業に精通した弁護士による分析により、感情的にならずに客観的な解決策を検討できます。不必要な争いを避け、効率的な解決を図ることができます。
解決方法の選択肢
- 示談による早期解決
- 調停・仲裁による和解的解決
- 訴訟による権利実現
- 行政機関への申立て
交渉力の向上
弁護士が交渉に関与することで、相手方の対応も変化し、より建設的な解決に向けた話し合いが可能になります。特に法的根拠に基づく主張は、相手方に対する説得力が格段に向上します。
5-3. 経営リスクの軽減
損害の最小化
適切な法的対応により、トラブルによる損失を最小限に抑えることができます。特に代金回収や損害賠償請求については、早期の法的対応が回収可能性を大きく左右します。
具体的な効果
- 代金回収率の向上
- 損害賠償額の適正化
- 工期遅延による損失の軽減
- 行政処分の回避・軽減
事業継続性の確保
深刻な法的トラブルは、企業の存続そのものを脅かす可能性があります。弁護士による適切なサポートにより、事業継続に必要な法的安定性を確保できます。
5-4. 人的・時間的負担の軽減
経営者の負担軽減
法的トラブルへの対応は、経営者にとって大きな精神的・時間的負担となります。経営者は、弁護士にトラブル処理を委任して本来の事業運営に集中できます。
従業員への影響軽減
トラブル対応に追われることで、従業員の業務に支障が生じることを防げます。特に中小企業では、経営者や幹部社員がトラブル対応に時間を取られることで、営業活動や現場管理に影響が出る場合があります。
6. 弁護士法人リブラ法律事務所のサポート内容
6-1. 建設業特化型の法務サービス
包括的な予防法務サポート
弁護士法人リブラ法律事務所では、建設業界の特性を深く理解した弁護士が、元請け業者の皆様に最適な法務サポートを提供しています。
契約書作成・レビューサービス 建設業法に完全準拠した契約書の作成をはじめ、既存契約書の法的リスクチェックを行います。特に中小企業では自社で適切な契約書を作成することが困難な場合が多いため、専門的なサポートが大きな価値を提供します。
コンプライアンス体制構築支援 建設業法、労働関連法令、独占禁止法・取適法など、建設業に関わる各種法令の遵守体制構築をサポートします。法改正への対応や社内研修の実施も含めた包括的なサービスを提供しています。
リスク管理システムの導入支援
法務チェックリストの作成 日常業務において法的リスクを早期発見するためのチェックリストを、お客様の事業内容に合わせてカスタマイズして作成します。これにより、法律問題の専門家でない現場担当者でも、リスクの早期発見が可能になります。
危機管理マニュアルの整備 トラブル発生時の初期対応手順を明文化したマニュアルの作成をサポートします。緊急時の連絡体制、証拠保全の方法、初期対応の注意点などを具体的に規定することで、適切な初期対応を確保できます。
6-2. トラブル解決における実践的サポート
迅速な初期対応
建設業のトラブルは時間との勝負という側面があります。当事務所では、緊急事態には24時間以内の初期対応を心がけ、被害の拡大防止に努めています。
緊急時対応フロー
- 電話・メールによる緊急相談受付
- 72時間以内の詳細打ち合わせ実施
- 証拠保全と初期対応策の立案
- 相手方との交渉開始
多角的な解決アプローチ
単に法的な正当性を主張するだけでなく、お客様の事業継続性を最優先に考えた現実的な解決策を提案します。
解決手法の選択肢
- 任意交渉による早期解決
- 建設業界団体による調停・あっせん
- 民事調停・仲裁の活用
- 民事訴訟による権利実現
- 行政機関への申立て・相談
6-3. 専門家ネットワークとの連携
技術専門家との協働
当事務所では、一級建築士、構造設計士、施工管理技士、不動産鑑定士など、建設業に関わる各分野の専門家とのネットワークを構築しています。
連携による効果
- 技術的争点の正確な分析
- 現場調査の適切な実施
- 損害額の客観的算定
- 専門的意見書の作成
業界団体・行政機関との関係
建設業界の各種団体や監督行政機関との良好な関係を活かし、業界全体の動向を踏まえた適切なアドバイスを提供します。
6-4. 中小企業に優しい料金体系
明確で予測可能な費用設定
中小規模の建設会社でも安心してご利用いただけるよう、明確で予測可能な料金体系を採用しています。
料金メニュー例
- 顧問契約:月額5万円〜(規模に応じて調整)
- 契約書作成:1件10万円〜
- 代金回収事件:着手金10万円〜、成功報酬10%〜
6-5. 継続的なサポート体制
顧問契約による包括サポート
月額顧問契約により、日常的な法律相談から緊急時の対応まで、包括的なサポートを提供します。顧問契約をご利用いただくことで、以下のようなメリットがあります。
顧問契約の特典
- 法律相談料の優遇
- 契約書チェックの迅速対応
- 緊急時の優先対応
- 社内研修の実施
- 法改正情報の定期提供
事業成長に応じたサポート
中小企業から中堅企業への成長過程で生じる法的課題について、段階的なサポートを提供します。事業規模の拡大に伴う許可要件の変更、組織体制の見直し、新規事業展開時の法的検討など、成長戦略に応じた法務サポートを行います。
まとめ:建設業における法的リスク管理の重要性
2025年現在、建設業界を取り巻く環境は激変しています。働き方改革、DXの推進、人材不足、資材高騰といった課題に直面する中で、元請け業者には従来以上に高度なリスク管理能力が求められています。
法的トラブルは一度発生すると、その解決に多大な時間とコストを要するだけでなく、企業の信用失墜や事業継続への深刻な影響をもたらす可能性があります。だからこそ、「問題が起きてから対応する」のではなく、「問題を起こさないための予防策」に重点を置いた法務体制の構築が不可欠です。
建設業に精通した弁護士との継続的なパートナーシップは、単なるリスク回避にとどまらず、事業の持続的成長を支える重要な基盤となります。法的な安定性を確保することで、経営者は安心して事業拡大に取り組むことができ、従業員も安定した環境で働くことができます。
弁護士法人リブラ法律事務所は、建設業界の発展に貢献するため、元請け業者の皆様に最適な法務サポートを提供し続けてまいります。どのような些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。私たちは、皆様の事業の成功と持続的発展を全力で支援いたします。
お問い合わせ・ご相談について
お問い合わせは、お電話(097-538-7720)またはウェブサイト
の相談フォームから承っております。建設トラブルでお悩みの方は、今すぐご連絡ください。
Last Updated on 10月 3, 2025 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |





