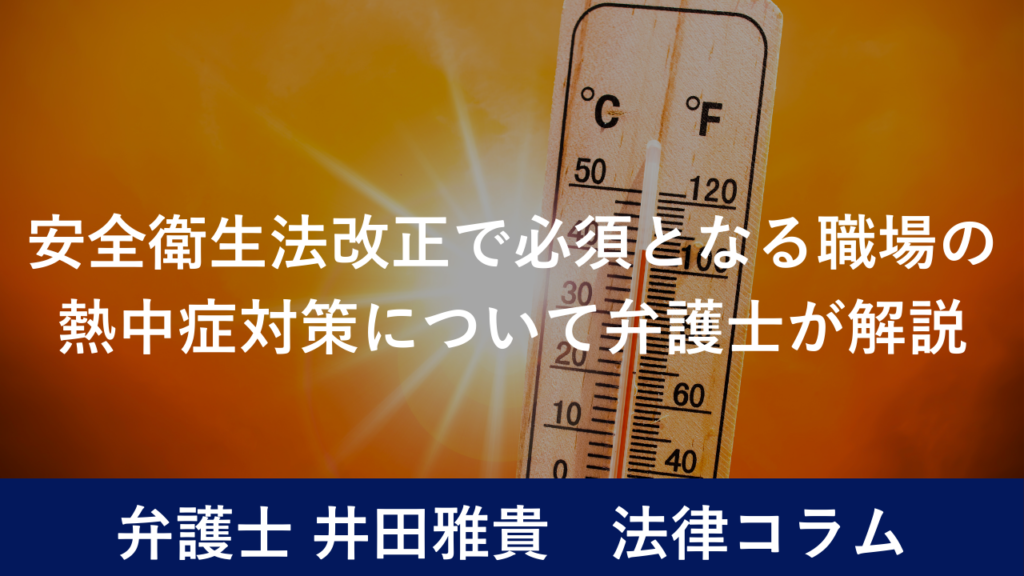
1 職場の熱中症対策を強化する意義と本稿の狙い
近年、夏季における記録的な猛暑が常態化し、職場での熱中症による労働災害が深刻な問題となっています。熱中症は、適切な予防策を講じれば防げる災害でありながら、重篤な後遺症が生じることや、最悪の場合、死に至るケースも後を絶ちません。企業にとって、従業員の安全と健康を守ることは、労働契約法や労働安全衛生法に基づく基本的な法的義務(安全配慮義務)であると同時に、企業の社会的責任(CSR)や持続的な事業活動の観点からも極めて重要です。
熱中症による労働災害が発生した場合、企業は被災した従業員やその遺族に対する損害賠償責任を負う可能性があるだけでなく、労災保険料の増加、行政による指導や処分、さらには悪質な場合には刑事責任を問われるリスクも抱えています。加えて、事故発生による生産性の低下、企業イメージの毀損、従業員の士気低下など、有形無形の甚大な損害を被る可能性があります。
本稿では、労働安全衛生法の改正動向も踏まえつつ、職場における熱中症対策の重要性を法的観点から解説し、企業が取るべき具体的な対策、対策を怠った場合のリスク、そして弁護士が提供できる実務的なサポートについて、網羅的に解説することを目的とします。 経営者、人事労務担当者、安全衛生担当者の皆様が、本稿を読まれたうえ、自社の熱中症対策を見直し、強化するための一助となれば幸いです。
2 安全衛生法改正の動向と企業の安全配慮義務・法的責任の概要
労働安全衛生法(安衛法)は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。近年の気候変動に伴う猛暑の頻発化と熱中症リスクの高まりを受け、国は安衛法関連法令の改正等を通じて、熱中症対策の強化を企業に求めています。
特に、WBGT(暑さ指数(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature、以下同じ意味です。)基準値を超える場所での作業における措置義務の明確化や、作業環境測定の義務化などが検討・実施されています。(※具体的な改正内容は最新の情報をご確認ください)
これらの法改正の動きは、企業が負うべき「安全配慮義務」の内容をより具体化し、その履行を強く求めるものです。安全配慮義務とは、判例法理上確立された考え方で、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負う」というものです(労働契約法第5条にも明文化)。
熱中症対策に関して言えば、企業は、作業環境の実態(温度、湿度、輻射熱等)を把握し、WBGT値等に基づいたリスク評価を行い、作業時間の短縮、休憩時間の確保、水分・塩分の補給、適切な服装の指示、健康状態の確認、労働者への教育、救急体制の整備など、具体的かつ実効性のある措置を講じる義務があります。この義務を怠り、その結果として労働者が熱中症に罹患した場合、企業は債務不履行(安全配慮義務違反)または不法行為に基づく損害賠償責任を問われることになります。さらに、重大な事故を引き起こした場合には、労働基準監督署による調査、行政指導、是正勧告、場合によっては業務上過失致死傷罪等での刑事責任追及(書類送検など)の対象となる可能性もあります。
3 現場の実態とよくある課題・疑問
(1)現場実態を踏まえた熱中症リスクと対策の課題整理
熱中症リスクが高い職場は多岐にわたります。建設現場、造船所、製鉄所などの屋外作業、高温の炉やボイラーを扱う工場、空調設備が不十分な倉庫や物流センター、ビニールハウス等での農作業、警備業務、配送業務、さらには近年増加しているフードデリバリー業務なども注意が必要です。また、屋内であっても、厨房、機械室、熱を発する機器の周辺なども高温多湿環境となりやすく、リスクは潜んでいます。
現場における課題としては、WBGT等の客観的な指標に基づいたリスク管理が徹底されていない、作業計画や人員配置が酷暑を前提としていない、休憩場所が確保されていない、あるいは適切でない(日陰がない、冷房がない等)、水分・塩分補給の重要性が認識されていない、作業員自身が体調不良を言い出しにくい雰囲気がある、管理監督者が熱中症の初期症状を見逃してしまう、高齢者や持病のある者、経験の浅い若年者など、特に配慮が必要な労働者への対策が不十分である、といった点が挙げられます。また、コスト面や生産性への影響を懸念して対策に踏み切れないという経営判断の問題も散見されます。
(2)企業から弁護士に寄せられる熱中症対策に関する代表的な相談内容
弁護士のもとには、熱中症対策に関して様々な相談が寄せられます。「法改正で具体的に何が変わるのか、自社は何をすべきか」「WBGTを測定しているが、基準値を超えた場合の具体的な対応がわからない」「休憩時間を増やしたいが、作業が遅れる。法的にどこまで求められるのか」「従業員が指示に従わず、水分補給を怠る場合にどうすればよいか」「下請け業者の作業員が熱中症になった場合、元請けにも責任はあるのか」「熱中症対策にかかる費用はどこまで負担すべきか」「万が一、労災事故が起きてしまった場合の対応を知りたい」といった、法的な義務の範囲、具体的な対策の進め方、労務管理上の課題、事故発生後の対応など、内容は多岐にわたります。これらの相談は、多くの企業が熱中症対策の重要性を認識しつつも、その具体的な実践方法や法的リスクの評価に悩んでいる現状を示唆しています。
(3)WBGT(暑さ指数)基準値の管理・運用に関する具体的な疑問点
WBGTは、人体の熱収支に影響の大きい「気温」「湿度」「輻射熱(日射など)」を取り入れた、熱中症リスクを評価するための指標です。安衛法関連のガイドライン等では、WBGTの基準値(例:作業強度に応じて25℃~31℃など)に応じた作業の中止や休憩時間の確保等が推奨・義務付けられています。
企業からは、「WBGT計はどこに設置すべきか?」「測定頻度は?」「基準値を超えたら、どのような作業を、どの程度制限すべきか?」「作業環境的にWBGT値を下げられない場合はどうするのか?」といった具体的な管理・運用に関する疑問が多く聞かれます。
WBGTの測定場所は、実際に労働者が作業している場所(またはそれに準ずる場所)が原則であり、高さなども考慮が必要です。測定頻度は作業内容や環境の変化に応じて適切に設定し、記録を残すことが重要です。基準値を超えた場合の措置は、作業強度、連続作業時間、個々の労働者の状態などを考慮して、作業時間の短縮、休憩時間の増加、作業内容の変更、場合によっては作業中止を判断する必要があります。環境改善が困難な場合は、より頻繁な休憩、空調服等の個人用保護具の活用、作業人数の増加によるローテーションなどが代替策として考えられます。
(4)休憩時間の確保・見直し、適切な服装ルール設定に関する相談
熱中症予防には、適切なタイミングと頻度での休憩、そして十分な水分・塩分補給が不可欠です。特にWBGT基準値を超える環境下では、通常の休憩時間に加えて、作業時間中に短い休憩(クールダウン)を設けることが推奨されます。企業からは、「どの程度の頻度・長さの休憩が必要か」「休憩場所はどのような設備が必要か」「休憩中の活動(スマホ利用など)をどこまで許容すべきか」といった相談があります。休憩時間はWBGT値や作業強度に応じて具体的に定め、周知徹底することが重要です。休憩場所は、日差しを避けられ、できれば冷房設備や送風機、冷たい飲料が用意された快適な環境が望ましいです。
服装に関しても、「安全基準を満たしつつ、通気性の良い作業着を導入したいがコストがかかる」「ヘルメット着用義務があるが、熱がこもる」「空調服の導入を検討しているが、効果や管理方法は?」といった相談が寄せられます。企業は、作業の安全性と快適性を両立させる服装規定を検討する必要があります。通気性・吸湿性・速乾性に優れた素材の採用、ヘルメット内部の通気改善策(インナーパッド等)、ファン付き作業着(空調服)の導入などは有効な対策ですが、導入にあたっては費用対効果やメンテナンス、バッテリー管理なども考慮し、必要に応じて従業員代表との協議も行うべきでしょう。
(5)作業環境測定(WBGT測定)の義務化に向けた準備と対応
法改正により、特定の高温多湿作業場所(例:熱源の近く、多湿環境など)において、WBGT値の測定が義務付けられる動きがあります。
これに対応するため、企業はまず、自社のどの作業場所が測定義務の対象となる可能性があるかを特定する必要があります。その上で、適切なWBGT測定器を選定・購入(またはレンタル)し、測定資格者(作業環境測定士等、または社内での適切な教育を受けた者)による定期的な測定体制を構築しなければなりません。測定結果は記録・保存し、その結果に基づいて作業計画の見直しや必要な改善措置(換気、冷房、遮熱など)を講じる義務が生じます。測定機器の校正や、測定者の教育・訓練も継続的に行う必要があります。義務化に備え、早期に専門家(作業環境測定機関や労働衛生コンサルタント、弁護士等)に相談し、計画的に準備を進めることが賢明です。
*本稿の末尾に「職場におけるWBGT値に基づく熱中症予防のための対応措置」の目安と「作業強度に応じたWBGT基準値(管理値)」の目安を表にしてみました。参考までにご確認ください
4 熱中症対策を怠る法的リスク
(1)企業が独自判断で対策を行う場合に潜む法的な落とし穴
熱中症対策の重要性を認識していても、「コストを抑えたい」「これまでのやり方で問題なかった」といった理由から、自己流の対策や、ガイドライン等で推奨される水準に満たない対策で済ませてしまう企業が見受けられます。例えば、「水分補給は各自に任せている」「休憩は取らせているが、具体的な時間や場所は指示していない」「WBGTは測っているが、記録や具体的な対応策は不明確」といったケースです。
しかし、これらの不十分な対策は、法的な観点からは「安全配慮義務を尽くした」とは評価されない可能性が高いです。万が一、労働災害が発生した場合、裁判所や労働基準監督署は、企業が客観的なリスク評価(WBGT測定等)に基づき、具体的かつ実効性のある対策(作業管理、環境管理、健康管理、教育等)を体系的に講じていたかを厳しく判断します。独自判断による対策が、結果的に不十分であった場合、「予見可能であったにも関わらず、回避措置を怠った」として、企業の法的責任が問われるリスクが高まります。
(2)労災認定に伴う災害補償責任と民事上の損害賠償リスク
業務中に従業員が熱中症に罹患した場合、業務との間に相当因果関係が認められれば、労働者災害補償保険(労災保険)の給付対象となります。労災保険からは、治療費(療養補償給付)、休業中の賃金補償(休業補償給付)、後遺障害が残った場合の補償(障害補償給付)、死亡した場合の遺族への補償(遺族補償給付)などが支払われます。
注意すべきは、労災保険給付がなされたとしても、企業の責任がそれで全て免除されるわけではない、という点です。労災保険は、あくまで法律で定められた一定の基準に基づく補償であり、被災労働者が受けた全ての損害(特に精神的苦痛に対する慰謝料など)を填補するものではありません。企業に安全配慮義務違反(過失)が認められる場合には、被災労働者やその遺族は、労災保険給付だけではカバーされない損害について、企業に対して別途、民事上の損害賠償請求訴訟を起こすことが可能です。賠償額は、企業の過失の程度、被災者の損害の大きさ(後遺障害の程度、逸失利益等)、慰謝料などを考慮して算定され、場合によっては数千万円から一億円を超える高額なものとなるケースもあります。
(3)労働基準監督署による行政指導、送検の可能性
労働基準監督署(労基署)は、労働安全衛生法等に基づき、事業場への立入検査(臨検監督)を行い、法令違反や不適切な安全衛生管理が認められた場合には、行政指導(口頭または文書による改善指導)、是正勧告(期限を定めた具体的な改善命令)、使用停止命令(危険な機械設備等)などの行政処分を行う権限を持っています。
熱中症による労働災害が発生した場合、特に死亡災害や重篤な災害の場合には、労基署による詳細な調査が行われます。調査の結果、企業に重大な法令違反や悪質な安全配慮義務違反が認められ、かつ、その違反が事故の直接的な原因であると判断された場合には、労基署は関係者を業務上過失致死傷罪(刑法211条)等の容疑で検察庁に書類送検する可能性があります。送検され、起訴されれば、企業の代表者や安全衛生担当者などが刑事罰(罰金や禁固刑)を受けるリスクがあります。たとえ不起訴や無罪となったとしても、送検されたという事実自体が、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。
(4)安全配慮義務違反による訴訟
前述の通り、企業は労働契約に基づき、労働者の生命・身体の安全を確保する義務(安全配慮義務)を負っています。熱中症対策を怠り、労働者が罹患した場合、企業はこの義務に違反したとして、民事訴訟(損害賠償請求訴訟)を提起されるリスクがあります。
訴訟においては、原告(被災労働者側)が企業の安全配慮義務違反(注意義務違反=過失)と損害発生との間の因果関係を立証する必要があります。しかし、労働災害訴訟では、企業側が「どのような対策を講じていたか」という情報を多く持っていることから、実質的には、企業側が「十分な対策を講じており、過失はなかった(あるいは過失は軽微であった)」ことを具体的に主張・立証していく必要性が高まります。
裁判所は、WBGT値の把握状況、作業管理(休憩、作業時間、作業内容)、環境管理(冷房、遮蔽、換気)、健康管理(健康診断、日常の健康確認)、労働衛生教育の実施状況、緊急時の対応体制などを総合的に考慮し、企業の過失の有無や程度を判断します。対策が不十分と判断されれば、高額な損害賠償を命じられる可能性があります。
5 【事例研究】熱中症による労働災害とその背景要因
(1)熱中症による死亡災害の発生状況と典型的な要因分析
ここ数年、毎年のように職場での熱中症による死亡災害が発生しています。厚生労働省の統計によれば、特に建設業や製造業、運輸業、警備業などで多
く発生しています。死亡災害に至るケースでは、単一の原因だけでなく、複数の要因が複合的に絡み合っていることが少なくありません。
典型的な要因としては、①WBGT等の客観的指標に基づくリスク評価と、それに応じた作業計画の見直しが不十分、②適切な休憩場所の未確保や、休憩・水分補給の指示・管理の欠如、③管理監督者や同僚による初期症状の見落とし、または本人が体調不良を訴えにくい職場環境、④緊急時の連絡・搬送体制の不備による対応の遅れ、⑤個々の労働者の健康状態(持病、睡眠不足、体調不良等)への配慮不足、⑥安全衛生教育の不足による労働者本人の予防意識の低さ、などが挙げられます。これらの要因を理解し、自社の状況に照らして対策を講じることが、悲劇を防ぐ鍵となります。
[事例1] 屋外建設現場におけるWBGT把握不足と救急搬送遅延
猛暑日の昼過ぎ、屋外の建設現場で作業していたベテラン作業員Aさんが突然倒れ、意識不明となりました。当日のWBGTは危険レベルに達していましたが、現場では定期的な測定や、それに応じた作業中止・休憩指示が行われていませんでした。休憩場所は用意されていましたが、作業場所から遠く、利用しにくい状況でした。
Aさんは、午前中から体調不良を自覚していましたが、「工期が遅れているから」と無理をして作業を続けていました。倒れた際、近くにいた同僚は熱中症の知識が乏しく、初期対応が遅れました。さらに、現場事務所との連絡も手間取り、救急車の要請までに時間がかかりました。結果として、Aさんは重度の熱中症と診断され、長期の入院と後遺障害が残りました。
この事例では、WBGT管理の不徹底、休憩場所の不備、作業員の無理な作業、周囲の認識不足、緊急連絡体制の不備が複合的に作用したと考えられます。
[事例2] 高温環境下の倉庫内作業における初期症状の見落としと管理体制不備
空調設備のない大規模な倉庫内で、ピッキング作業に従事していた派遣社員Bさんが、作業中にめまいと吐き気を訴えましたが、現場リーダーは「少し休めば大丈夫だろう」と、倉庫内の片隅で休ませるに留めました。倉庫内は蒸し暑く、WBGT値も高い状態でしたが、会社として具体的な暑熱対策(スポットクーラー設置、休憩時間の増加等)は講じられていませんでした。
リーダー自身も熱中症の初期症状に関する知識が不足していました。Bさんはその後、症状が悪化し、意識を失って倒れているところを発見されましたが、発見が遅れたこともあり、重症化しました。この事例では、作業環境の劣悪さ、管理監督者の知識不足と初期症状の軽視、派遣社員という立場から本人が強く不調を訴えられなかった可能性、組織的な対策の欠如が問題点として挙げられます。
[事例3] 農業現場における休憩・水分補給指導の欠如と無防備な作業
個人経営の農園で、夏季の収穫作業を手伝っていたアルバイトの学生Cさんが、ビニールハウス内で作業中に意識を失い、救急搬送されました。
当日は高温多湿で、ハウス内はサウナのような状態でしたが、経営者はWBGT等の測定を行っておらず、休憩や水分補給について具体的な指示もしていませんでした。Cさん自身も、農業経験が浅く、熱中症のリスクを十分に認識していませんでした。帽子は被っていましたが、通気性の悪い服装で、長時間作業を続けていました。この事例は、比較的小規模な事業場であっても、基本的な熱中症対策(環境把握、作業管理、教育)が不可欠であることを示しています。経営者の「これまでは大丈夫だった」という経験則への過信が、事故を招いた可能性があります。
[事例4] 経験の浅い若年労働者に対する配慮不足と対応の遅れ
工場に就職したばかりの若年労働者Dさんは、高温となるラインでの作業に慣れておらず、連日の猛暑で体力を消耗していました。
ある日、作業中に気分が悪くなりましたが、周囲の先輩に迷惑をかけたくない、また「根性がない」と思われることを恐れて言い出せず、作業を続けました。現場の班長は、Dさんの顔色が悪いのには気づいていましたが、「新人だから疲れているのだろう」程度に考え、特別な配慮はしませんでした。
その後、Dさんはライン上で倒れ、熱中症と診断されました。この事例は、経験の浅い労働者や、職場環境に慣れていない労働者に対しては、特に注意深い観察と声かけ、そして体調不良を気軽に相談できる雰囲気づくりが重要であることを示唆しています。新人教育において、熱中症のリスクと対処法を具体的に教えることも不可欠です。
[事例5] 委託先・請負業者に対する安全管理体制の不備が招いた事故
大規模なイベント会場の設営作業において、元請け企業A社は、複数の下請け企業に作業を委託していました。
猛暑の中での作業でしたが、A社は自社の従業員に対する熱中症対策は指示していたものの、下請け企業の作業員に対する具体的な指示や管理(WBGT情報の共有、統一的な休憩時間の指示、救護体制の整備等)は十分に行っていませんでした。
その結果、異なる下請け企業に所属する複数の作業員が、同日、相次いで熱中症を発症し、うち1名は重症となりました。この事例では、元請け企業が、自社の労働者だけでなく、関係請負人の労働者も含めた作業全体の安全衛生管理を統括調整する義務(安衛法第29条等)を十分に果たしていなかったことが問題となります。混在作業場所における安全管理体制の構築と、委託先に対する明確な指示・指導の重要性を示しています。
6 対策不備がもたらす企業損害と弁護士によるサポート
(1)熱中症対策を怠った場合の企業損害(直接・間接)と弁護士介入の効果
熱中症対策の不備が労働災害を引き起こした場合、企業が被る損害は、被災者への損害賠償金や労災保険料の増加といった直接的な金銭負担だけではありません。事故対応に要する時間的・人的コスト、生産ラインの停止や工期の遅延による機会損失、行政対応、訴訟対応といった間接的な負担も発生します。さらに、”ブラック企業”とのレッテルの流布による企業イメージの低下、社会的信用の失墜は、採用活動の困難化、取引関係への悪影響、株価の下落など、長期的かつ深刻なダメージを与えかねません。従業員の士気低下や、他の従業員の離職を招く可能性もあります。
万が一、事故が発生してしまった場合、早期の段階で弁護士が介入することには大きな意義があります。
弁護士は、法的な観点から状況を正確に把握し、証拠保全、関係者へのヒアリング、行政(労基署等)への対応、被災者側との交渉などを適切に行うことで、事態の悪化を防ぎ、企業の損害を最小限に抑えるためのサポートを提供します。感情的な対立を避け、冷静かつ法的に妥当な解決を目指すことが可能になります。
(2)労災保険料率の上昇、企業イメージ・社会的信用の毀損リスク
労災保険制度には、個々の事業場の労働災害発生状況に応じて保険料率や保険料額を増減させる「メリット制」が適用される場合があります(一定規模以上の事業場等)。死亡災害や重篤な後遺障害が残る災害など、重大な労働災害を発生させた場合、翌年度以降の労災保険料が大幅に増加する可能性があります。これは、長期にわたるコスト負担増となります。
また、現代社会においては、企業のコンプライアンス意識や安全衛生への取り組みが、投資家、取引先、消費者、そして求職者から厳しく評価されます。重大な労働災害、特に予防可能であったはずの熱中症による事故を発生させたという事実は、ニュース報道やSNSなどを通じて瞬時に拡散し、「従業員の安全を軽視する企業」というネガティブなイメージを定着させかねません。一度損なわれたブランドイメージや社会的信用を回復するには、多大な時間と労力、コストが必要となります。
(3)刑事責任回避のための初動支援
熱中症による死亡災害など、重大な結果が発生した場合、警察や労働基準監督署による捜査が行われ、企業の代表者や現場の責任者が業務上過失致死傷罪等で立件される可能性があります。このような事態を回避するためには、事故発生直後からの適切な初動対応が極めて重要です。
弁護士は、事故発生直後から、①事実関係の正確な把握と証拠の保全、②関係者(被災者、目撃者、担当者等)からの事情聴取と記録化、③警察や労基署の調査・捜査に対する適切な対応(供述内容の検討、資料提出の判断等)、④今後の法的リスクの評価と対応方針の策定、⑤被災者や遺族への誠意ある対応と早期の示談交渉の開始などを支援します。捜査機関に対して、企業として事故原因の究明と再発防止策に真摯に取り組んでいる姿勢を示すと共に、法的な観点から企業の過失の程度や予見可能性について的確に主張することで、不起訴処分の獲得や、起訴された場合でも量刑の軽減を目指します。
(4)民事訴訟における損害賠償減額交渉の要点
被災した従業員やその遺族から、民事上の損害賠償請求を受けた場合、企業としては、訴訟に至る前の示談交渉、または訴訟における和解交渉を通じて、早期かつ円満な解決を目指すことが望ましいです。
弁護士は、企業の代理人として、被災者側との交渉に臨みます。交渉の要点としては、①事故発生状況と原因に関する事実認定の共有、②企業が講じていた安全対策の内容と、それが法的義務に照らしてどの程度であったかの評価(過失の程度の主張)、③被災者側の過失(自己管理の不注意等)の有無とその割合(過失相殺の主張)、④労災保険給付との関係(損益相殺)、⑤後遺障害の程度や逸失利益、慰謝料等の損害額の算定の妥当性、などを法的な根拠に基づいて主張・検討します。企業側の主張を裏付ける客観的な証拠(作業記録、WBGT測定記録、教育記録、規程類など)を提示し、粘り強く交渉することで、法的に妥当な範囲での賠償額での解決(減額交渉)を目指します。
6 弁護士による実務的な熱中症対策強化支援
(1)弁護士が提供する実効性のある熱中症対策強化の実務サポート概要
弁護士の役割は、事故が起きた後の対応だけではありません。むしろ、事故を未然に防ぐための予防法務、すなわち実効性のある熱中症対策の構築・強化を支援することに、より大きな価値があります。弁護士は、最新の法改正や裁判例、ガイドライン等を踏まえ、企業の業種、規模、作業環境の実態に合わせて、法的な要求水準を満たすだけでなく、現場で実際に機能する具体的な対策を提案・支援します。安全衛生管理規程の整備から、教育プログラムの策定、緊急時対応フローの構築、さらには新しい技術(ウェアラブルデバイス等)の導入支援まで、多角的なサポートを提供します。
(2)法改正に対応した安全衛生管理規程、作業マニュアル等の改訂支援
熱中症対策を組織的かつ継続的に実施するためには、その根拠となる社内規程(就業規則、安全衛生管理規程、作業手順書、マニュアル等)を整備・改訂することが不可欠です。弁護士は、安衛法や関連ガイドラインの要求事項、最新の法改正動向を反映させ、企業の現状に即した規程の作成・改訂を支援します。具体的には、WBGT基準値に応じた作業管理基準(作業中止、休憩時間の延長等)、水分・塩分補給の具体的な方法とタイミング、作業員の健康状態確認の手順、異常発見時の報告・連絡体制、緊急時の救護・搬送手順などを明確に規定します。また、これらの規程が、他の社内規程や労働協約との整合性が取れているか、法的に有効なものとなっているかについてもチェックします。
(3)従業員向け熱中症予防教育・研修プログラムの設計と実施、運用状況の監査
熱中症対策の実効性を高めるためには、経営層から管理監督者、そして一般の作業員一人ひとりが、熱中症のリスク、予防策、発生時の対処法について正しい知識を身につけることが重要です。弁護士は、企業の業種や対象者(新人、管理者、外国人労働者等)に合わせて、効果的な教育・研修プログラムの設計を支援します。プログラム内容には、熱中症のメカニズム、症状、WBGTの意味と活用法、具体的な予防行動(水分補給、休憩、服装)、体調管理の重要性、異常発見時の報告義務、応急手当の方法などを含めます。また、教育が計画通りに実施され、その内容が従業員に理解・浸透しているかを定期的に確認(監査)し、必要に応じてプログラム内容の見直しを提案することも可能です。
(4)熱中症発生時の緊急対応フロー(救護、連絡体制等)の法的妥当性チェック
万が一、従業員が熱中症を発症した場合、迅速かつ適切な初期対応(応急手当、救急搬送)が生死や後遺障害の有無を左右します。そのため、事前に緊急時対応フローを明確に定め、関係者全員が理解・習熟しておくことが極めて重要です。弁護士は、企業が作成した緊急時対応フローについて、法的な観点からその妥当性をチェックします。
具体的には、①症状に応じた応急手当(涼しい場所への移動、衣服を緩める、身体を冷やす、水分補給等)の手順が明確か、②発見者から管理者、救急隊への連絡体制・報告ルートが確立されているか、③救急車要請の判断基準が明確か、④搬送先医療機関との連携は考慮されているか、⑤事故発生後の社内報告、労基署への報告手順は定められているか、などを確認し、改善点を指摘します。
7 弁護士と進める具体的な安全衛生体制構築
(1)弁護士が法的観点からサポートする具体的な安全衛生体制構築策
弁護士は、個別の対策支援に留まらず、企業全体の安全衛生管理体制の構築を法的側面からサポートします。安全衛生委員会(または衛生委員会)の適切な運営支援(議題設定、審議内容の記録等)、安全衛生管理規程と現場の実態との整合性チェック、リスクアセスメントの実施と結果に基づく対策の優先順位付け、PDCAサイクル(計画-実行-評価-改善)に基づいた継続的な改善活動の導入などを助言します。法的な義務の履行はもちろんのこと、企業の安全文化を醸成し、従業員の安全意識を高めるための体制づくりを目指します。
(2)「クールワークキャンペーン」等の社内啓発活動の企画・運用支援
熱中症予防に関する知識や意識を社内に浸透させるためには、ポスター掲示、朝礼での呼びかけ、社内報での特集、安全標語の募集といった啓発活動(例:「クールワークキャンペーン」)が有効です。弁護士は、これらのキャンペーンの企画段階から関与し、伝えるべきメッセージの内容が法的要求事項や企業の安全方針と整合しているか、誤解を招く表現はないかなどをチェックします。また、キャンペーンが単なる形式的なものに終わらず、従業員の具体的な行動変容に繋がるような工夫(具体的な行動目標の設定、成功事例の共有、インセンティブ導入等)についても、法的リスクを踏まえつつアドバイスを提供します。
(3)ウェアラブルデバイス等を活用した作業員の健康状態モニタリング導入支援と留意点
近年、心拍数や深部体温などを測定できるウェアラブルデバイスを活用し、作業員の体調変化をリアルタイムで把握しようとする動きがあります。これらのデバイスは、熱中症の早期発見や重症化予防に繋がる可能性がある一方で、導入・運用にあたっては、プライバシー保護の観点から慎重な検討が必要です。弁護士は、デバイス導入の目的、収集するデータの種類と範囲、データの利用目的、保管期間、管理体制、従業員への説明と同意取得の方法などについて、個人情報保護法等の法令に適合しているかを確認し、適切な運用ルール(プライバシーポリシー等)の策定を支援します。技術の利便性と個人の権利保護のバランスを取りながら、安全管理に資する活用方法を検討します。
(4)休憩時間延長や作業中止基準に関する労使協定締結・変更時の法的助言
夏季の酷暑期間における休憩時間の延長、WBGT値に基づく一斉休憩や作業中止基準の設定など、法定の基準を上回る労働条件や独自のルールを設ける場合、労働組合または労働者の過半数代表との間で労使協定を締結することが望ましい場合があります。また、就業規則の変更が必要となるケースもあります。弁護士は、これらの労使協定の内容が労働関係法令に違反していないか、協定の締結・変更手続きが適法に行われているか、協定内容が従業員に不利益とならないか(不利益変更に該当しないか)などをチェックし、労使間の円滑な合意形成と法的に有効な協定締結をサポートします。
8 顧問契約による継続的なコンプライアンス体制
(1)顧問弁護士契約による継続的な安全衛生コンプライアンス確保のメリット
熱中症対策を含む安全衛生管理は、一度規程を作ったり、教育を実施したりすれば終わり、というものではありません。法改正への対応、新たなリスクの発見、現場状況の変化、従業員の入れ替わりなどを踏まえ、継続的に見直しと改善を行っていく必要があります。顧問弁護士契約を締結することで、企業は、安全衛生に関する法的な疑問や課題が生じた際に、いつでも気軽に相談できる専門家を確保できます。弁護士が企業の事業内容や内部事情を継続的に把握することで、より実情に即した、迅速かつ的確なアドバイスが可能になります。単発での相談に比べて、中長期的な視点でのコンプライアンス体制構築や、突発的なトラブルへの迅速な対応が期待でき、結果的にコスト効率も高まる場合があります。
(2)定期的な現場リスクレビューと法改正動向を踏まえた是正措置の提案
顧問契約のサービスの一環として、弁護士が定期的に(例:月次、四半期ごと)企業の安全衛生担当者とミーティングを行い、最近のヒヤリハット事例、現場からの意見、作業内容の変更などをヒアリングし、潜在的な法的リスクをレビュー(評価)することが可能です。また、最新の法改正、通達、裁判例などの情報を提供し、それらが企業の安全衛生管理体制に与える影響を分析。その上で、現行の規程やマニュアル、運用方法について、具体的な是正措置や改善策をタイムリーに提案します。これにより、企業は常に最新の法的要求水準に対応した体制を維持しやすくなります。
(3)最新の法改正・通達に関する情報提供と社内規程の適時アップデート
労働安全衛生関連の法令や通達は、社会情勢の変化や新たな知見を反映して、頻繁に改正・更新されます。企業がこれらの最新情報を自力で常に把握し、適切に対応していくことは容易ではありません。顧問弁護士は、これらの法改正等の動向を継続的にウォッチし、企業に関連する重要な変更点があった場合には、速やかに情報提供を行います。さらに、その変更内容を踏まえ、就業規則や安全衛生管理規程、関連マニュアル等の見直し・改訂作業を具体的にサポートし、社内規程を常に最新かつ法的に有効な状態に保つお手伝いをします。
(4)万が一の労働災害発生時における迅速な初動対応と法的サポート
どれだけ対策を講じていても、不幸にして労働災害が発生してしまう可能性をゼロにすることはできません。万が一、熱中症による事故が発生した場合、顧問弁護士がいれば、電話一本で直ちに法的アドバイスを受けることが可能です。事故直後の混乱した状況下で、何をすべきか、何をしてはいけないのか、誰にどのように連絡・報告すべきかなど、冷静かつ的確な判断をサポートします。必要に応じて、弁護士が速やかに現場に赴き、状況把握、証拠保全、関係者対応、行政対応などを直接支援することも可能です。迅速かつ適切な初動対応は、その後の法的責任の範囲や、企業が受けるダメージの大きさを左右する上で極めて重要です。
9 おわりに:経営層が今すぐ行動すべき理由
(1) 法改正を踏まえ、経営者が熱中症対策に積極的に取り組むべき理由と相談窓口案内
本稿で解説してきた通り、職場における熱中症対策は、単なる努力目標ではなく、企業の法的義務であり、これを怠ることは重大な経営リスクに直結します。近年の法改正の動きは、この義務の履行を社会全体としてより強く求めていることの表れです。経営者の皆様には、熱中症対策を単なるコストではなく、従業員の生命と健康、ひいては企業の持続的な成長を守るための重要な「投資」と捉え、リーダーシップを発揮して積極的に取り組んでいただくことを強く求めます。何から手をつけるべきか分からない、自社の対策が十分か不安がある、といった場合には、躊躇なく専門家にご相談ください。多くの法律事務所では、初回相談を無料で受け付けています。
(2)本格的な夏季シーズン到来前に具体的な対策を完了させる重要性
熱中症対策は、気温が高くなってから慌てて始めるのでは手遅れになる可能性があります。WBGT測定器の準備、休憩場所の整備、教育の実施、規程の見直し、緊急時対応フローの周知徹底など、実効性のある対策を講じるには、相応の準備期間が必要です。本格的な夏季シーズンを迎える前の、春先から計画的に準備を進め、梅雨明けまでには一通りの対策を完了させておくことが理想的です。早期の取り組みが、悲惨な事故を防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境を実現する鍵となります。
以上、当事務所でも、職場における熱中症対策に関するご相談を随時受け付けております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
【ご注意】
本記事は、職場における熱中症対策に関する一般的な情報提供を目的とするものであり、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。個別の事案については、必ず弁護士にご相談ください。
職場におけるWBGT値に基づく熱中症予防のための対応措置(目安)
WBGT値(℃) 危険度 対応措置(目安) 31 以上 危険 (運動は原則中止) 【原則】激しい作業や運動は中止。 ・特に持久的な作業や、身体負荷の大きい作業は避ける。 ・頻繁な休憩を義務付け、冷房設備のある涼しい場所で休憩させる。 ・作業時間の大幅な短縮、または作業の延期・中止を検討。 ・水分・塩分の積極的かつ定期的な摂取を指示・管理。 ・作業者相互および管理者による継続的な健康状態の確認を徹底。 28 ~ 31未満 厳重警戒 【激しい作業・運動は極力避ける】 ・激しい作業や長時間の連続作業は、可能な限り他の時間帯に移行するか、負荷を軽減。 ・休憩時間を通常より長く、頻繁に確保。(例:1時間あたり10~20分以上の休憩) ・涼しい休憩場所を確保。 ・水分・塩分のこまめな摂取を強く推奨・指示。 ・作業者間の相互の声かけを励行し、体調不良の兆候を見逃さない。 ・体調不良を訴えた者には、作業軽減や休憩指示を行う。 25 ~ 28未満 警戒 【積極的な休憩と水分補給】 ・中等度以上の作業(ややきついと感じる程度以上)では、定期的な休憩(例:30分~1時間に1回程度)を意識的に取るよう指示。 ・自覚的な水分・塩分補給を促すだけでなく、定期的な補給タイムを設けることも有効。 ・作業負荷の軽減や、作業ペースの調整を検討。 ・個々の作業者の体調変化に注意を払う。 25 未満 注意 【油断せず、基本的な対策を】 ・一般的には安全な範囲とされるが、油断は禁物。 ・作業強度や個人の体調に応じて、適宜水分補給を行うよう推奨。 ・湿度が高い場合や、体調が万全でない者、暑熱順化が不十分な者には、特に配慮が必要。
【注意点】
- この表は一般的な目安を示すものであり、実際の対応は、作業の強度(軽作業、中等作業、重作業など)、作業者の暑熱順化の度合い、健康状態、服装、年齢、持病の有無、作業場所の通気性や日照条件などを総合的に考慮して決定する必要があります。
- 特に、身体負荷の大きい作業を行う場合は、より低いWBGT値でも危険度が高まるため、表の目安よりも厳しい基準で対応する必要があります。
- 厚生労働省や各業界団体などが示すガイドラインや、専門家(労働衛生コンサルタント等)の助言も参考に、自社の状況に合わせた具体的な作業管理基準を策定・運用することが重要です。
- WBGT値は、作業場所における実測値を用いることが原則です。
作業強度に応じたWBGT基準値(管理値)の目安
作業強度区分 作業の例 代謝率相当量 (M) [W/m²] WBGT基準値(℃) (熱に順化している人) WBGT基準値(℃) (熱に順化していない人) Ⅲ 激しい作業 (Heavy Work) 連続したシャベル・スコップ作業、つるはし作業、重い資材の連続運搬、激しい運動を伴う作業 200 超 ~ 260 以下 26 ℃ 25 ℃ Ⅱ 中等度作業 (Moderate Work) 断続的な荷物の運搬・積み下ろし、一般的な建設・土木作業、農作業(草刈り等)、やや速い歩行を伴う作業 130 超 ~ 200 以下 28 ℃ 26 ℃ Ⅰ 軽作業 (Light Work) 座位または立位での軽作業(部品組立、検査等)、事務作業、運転、通常の歩行 130 以下 30 ℃ 29 ℃ (※28℃とする資料もあり) 0 安静 (Rest) 座位で安静にしている状態 65 程度 31 ℃ 30 ℃
【補足事項】
- WBGT基準値(管理値)とは: この値を超える環境下では、熱中症のリスクが高まるため、作業時間の短縮、休憩時間の確保、作業負荷の軽減などの熱中症予防対策が必要となる目安のWBGT値です。この値以下であれば安全という意味ではありません。
- 熱に順化している人: その暑熱環境で数日~1週間程度、毎日作業(または運動)を行い、体が暑さに慣れている状態の人を指します。
- 熱に順化していない人:
- その暑熱環境での作業が初めて、または数日間中断した後(休暇明け、出張帰り、病み上がり等)の人。
- 急に暑くなった時期(梅雨明け直後など)で、まだ身体が暑さに慣れていない場合。
- 一般的に、熱に順化していない人に対しては、より低いWBGT基準値を適用し、慎重な管理が必要です。
- 代謝率相当量(M): 作業による身体活動の強度(熱産生量)を示す指標です。作業内容によって異なるため、より正確な管理のためには、作業ごとの代謝率を考慮することが望ましいです。(表中の値は目安です)
- 出典等に関する注意: この表は、ISO 7243や(公社)日本産業衛生学会(JSOH)の許容濃度等に関する勧告などを参考に作成した一般的な目安です。必ず最新の公的ガイドライン(厚生労働省等)や専門機関の情報を確認し、自社の作業実態に合わせて適切な管理基準を設定してください。
- 個体差への配慮: 年齢、健康状態、持病、肥満度、服装などによって熱中症のリスクは異なります。基準値はあくまで目安とし、個々の労働者の状態にも十分配慮することが重要です。
Last Updated on 7月 23, 2025 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |





