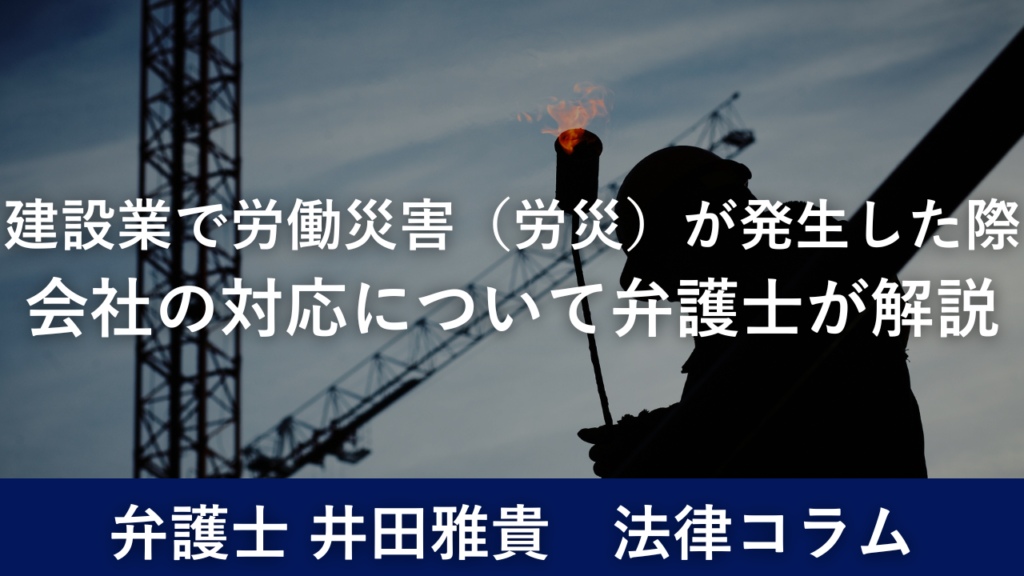
本稿の要旨を音声で確認したい場合はこちらから。
建設業は、日本の経済を支える重要な産業である一方で、他の産業に比べて労働災害(以下、「労災」といいます。)のリスクが高いという特性を持っています。ひとたび労災が発生すれば、負傷者の命に関わる重大な事態に発展する可能性があり、企業は法的・社会的に重い責任を負うことになります。
しかし、多くの建設業の経営者様は、日々の業務に追われ、労災発生時の具体的な対応や法的責任について、十分に把握しているとは言えないのではないでしょうか。
「労災が起きてしまったら、一体何をすればいいのか?」
「会社が負う責任の範囲はどこまでなのか?」
「損害賠償を請求されたら、どう対応すればいいのか?」
このような疑問や不安を抱える中小企業の社長様も少なくないはずです。
本稿では、建設業における労災リスクの実態から、万が一労災が発生してしまった際の緊急初動、法令に基づく報告義務、そして企業が負う民事上の損害賠償責任、さらには再発防止策に至るまで、弁護士の視点から詳しく解説します。そして、リブラ法律事務所が労災対応において、どのように貴社をサポートできるのかについても具体的にご説明いたします。
建設業における労災リスクと企業の責任
建設業特有の労災リスクと重大性
建設現場は、高所作業、重量物の運搬、危険な機械の使用など、常に危険と隣り合わせの環境です。そのため、墜落・転落、建設機械・クレーン等による事故、崩壊・倒壊、飛来・落下、感電など、様々な種類の労災が発生するリスクを抱えています。
厚生労働省の発表する労働災害発生状況を見ても、建設業における死傷者数は全産業の中でも高い水準にあり、特に死亡災害の発生率は顕著です。一度労災が発生すれば、負傷者の肉体的・精神的苦痛はもちろんのこと、最悪の場合、尊い命が失われる可能性もあります。
大分県労働基準監督署が発表した令和6年業種別労働災害発生状況(新型コロナウイルスり患除く)をみると、建設業における死傷者数・死亡者数は、それぞれ197名、1名であり、令和5年より減少しているものの、他の業種に比べると高止まりしている、と評価できます。
単に事故が起きたという事実だけでなく、その背後には、被災者とその家族の人生を大きく変えてしまうという重い現実があることを、私たちは常に認識しておく必要があります。
労災発生時に企業が負う法的・社会的責任
労災が発生した場合、企業は多岐にわたる責任を負うことになります。
- 刑事責任: 労働安全衛生法違反など、企業が安全配慮義務を怠った結果、労災が発生したと判断された場合、事業者や現場責任者個人が業務上過失致死傷罪などに問われ、罰金や懲役刑に処される可能性があります。
- 行政責任: 労働基準監督署による立ち入り検査や指導、是正勧告の対象となり、改善が見られない場合には、使用停止命令や作業停止命令など、事業運営に大きな影響を及ぼす行政処分を受けることもあります。また、建設業法に基づく監督処分(営業停止など)の対象となる可能性も否定できません。
- 民事責任: 被災者やその遺族から、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求を受ける可能性があります。これについては後述の「企業が負う民事上の損害賠償責任とその負担を減らすためにできること」で詳しく解説します。
- 社会的責任: 労災は、企業の信頼性やイメージに深刻なダメージを与えます。企業として安全管理体制が不十分であるとの批判を受け、取引先からの信用失墜、受注機会の喪失、優秀な人材の離職など、事業活動に甚大な悪影響を及ぼす可能性があります。
これらの責任は、企業の存続をも揺るがしかねない重大なものです。だからこそ、労災を未然に防ぐための努力はもちろんのこと、万が一労災が発生してしまった際の適切な対応が、企業の危機管理において極めて重要となるのです。
労災発生時の緊急初動と初期対応(事故発生直後~24時間以内)
労災が発生した際、事故発生直後から24時間以内の初動対応は、負傷者の生命に関わるだけでなく、その後の法的・行政的な対応、ひいては企業の責任範囲にも大きな影響を与えます。混乱しがちな状況だからこそ、冷静かつ迅速な行動が求められます。
負傷者の救護と緊急医療機関への搬送
何よりも最優先すべきは、負傷者の救護です。
- 安全確保: まず、負傷者自身や救護にあたる人が、さらなる危険にさらされないよう、周辺の安全を確保します。
- 応急処置: 負傷者の意識、呼吸、出血の有無などを確認し、必要に応じて止血や人工呼吸、心臓マッサージなどの応急処置を行います。
- 緊急連絡: 負傷者の状態に応じて、すぐに119番(救急車)に通報します。この際、事故の場所、負傷者の人数、負傷の状態などを具体的に伝えることが重要です。
- 医療機関への搬送: 救急隊の指示に従い、速やかに医療機関へ搬送します。意識がある場合は、負傷者に付き添い、状況を説明できるよう準備しておきましょう。
この段階での迅速かつ適切な対応が、負傷者の予後を左右するだけでなく、企業としての責任ある姿勢を示す上でも極めて重要です。
二次災害の防止と現場の安全確保
負傷者の救護と並行して、二次災害の防止と現場の安全確保を行います。
- 危険源の除去: 事故の原因となった機械の停止、電源の遮断、危険物の除去など、さらなる事故が発生する可能性のある危険源を排除します。
- 立ち入り禁止措置: 事故現場周辺には、関係者以外の立ち入りを厳重に制限するため、バリケードやロープなどで規制線を張ります。
- 作業の中止・点検: 事故の原因が特定できない場合や、同様の事故が発生するおそれがある場合は、関連する作業を一時的に中止し、設備の点検や安全確認を徹底します。
- 必要に応じた避難指示: 広範囲に影響を及ぼす可能性がある場合は、周辺の作業員や住民への避難指示も検討します。
これらの措置は、新たな被害者を出すことを防ぐだけでなく、事故原因の調査を適切に進めるための現場保存にも繋がります。
関係者への速やかな連絡・報告
事故発生後、速やかに適切な関係者への連絡・報告を行います。
- 社内連絡:
- 経営層・安全管理者: 直ちに事故発生を報告し、今後の対応について指示を仰ぎます。
- 現場責任者: 事故状況の詳細を把握し、報告内容を取りまとめます。
- 人事・総務部門: 労災保険の手続きや被災者への連絡窓口となります。
- 他部署の関連責任者: 必要に応じて情報共有を行います。
- 元請け・下請けへの連絡(建設業特有):
- 元請負業者と下請負業者の間で労災が発生した場合、それぞれの立場で速やかに相手方へ連絡し、情報共有を行います。特に、元請負業者は現場全体の安全管理責任を負うため、下請負業者の労災についても迅速に把握し、対応を協議する必要があります。
- 連携が不十分だと、その後の調査や手続きに支障をきたすだけでなく、責任関係が複雑化する原因となります。
- 関係官庁への連絡(人身事故の場合):
- 負傷者がいる場合、負傷の程度によっては、後述の労働基準監督署や警察への報告が必要になります。緊急性が高い場合は、事故発生の初期段階で電話等による速報も検討します。
- 被災者の家族への連絡:
- 負傷者の状態が落ち着き次第、速やかに被災者の家族に連絡し、事故の状況と現在の容態、搬送先の病院などを伝えます。この際、誠意と配慮をもって接することが重要です。
これらの連絡は、情報の錯綜を防ぎ、組織的な対応をするために不可欠です。
証拠の保全と初期情報の記録
事故発生直後から、証拠の保全と初期情報の記録を徹底することが極めて重要です。これは、後の事故原因究明、責任追及、損害賠償請求への対応において、決定的な役割を果たします。
- 現場写真・動画の撮影:
- 事故発生直後の現場の状況を、様々な角度から詳細に撮影します。時間の経過とともに状況は変化するため、できるだけ早い段階で撮影することが重要です。
- 負傷者の位置、事故の原因となった物体の状態、周辺の危険物、安全設備の状態、天候、照明など、あらゆる要素を記録します。
- デジタルカメラやスマートフォンで撮影する際は、撮影日時が記録される設定になっていることを確認しましょう。
- 関係者の証言・聞き取り:
- 事故の目撃者や、事故に関わった作業員、監督者などから、当時の状況について詳細な聞き取りを行います。
- 聞き取りは、できるだけ客観的な事実に基づいて行い、推測や憶測を排除します。
- 聞き取った内容は、日時、場所、話者、内容などを明確に記録し、可能であれば署名をもらっておくと良いでしょう。
- 関係書類の保全:
- 事故に関係するあらゆる書類(作業計画書、安全点検記録、機械の保守点検記録、作業指示書、作業員名簿、教育訓練記録、雇用契約書など)を漏れなく保全します。
- これらの書類は、安全管理体制の状況や、事故発生に至る経緯を明らかにする上で重要な証拠となります。
- その他物証の保全:
- 事故の原因となった機械の部品、保護具、使用されていた工具など、事故に関わる可能性のある物証は、改変されないように適切に保存します。
これらの記録・保全作業は、後の調査や法的手続きにおいて、企業の主張を裏付けるための重要な根拠となります。混乱の最中ではありますが、体系的に情報を収集・記録する体制を整えることが求められます。
法令に基づく報告義務と手続き(事故発生後~遅滞なく/原則14日・50日以内)
労災が発生した場合、企業は日本の法令に基づき、特定の機関に対して報告を行う義務があります。これらの報告義務を怠ると、罰則の対象となるだけでなく、企業の信頼性を損なうことにも繋がります。
労働基準監督署への報告
労働安全衛生法により、企業は特定の労災が発生した場合、所轄の労働基準監督署(以下、「労基署」といいます。)に報告する義務があります。
- 提出義務の対象となる労災:
- 死亡災害: 労災により労働者が死亡した場合。
- 休業災害: 負傷または疾病により、労働者が4日以上休業した場合。
- その他: 労基署が指定する特定の災害(例:特定機械等の破損事故など)。
- 報告書の様式と提出期限:
- 死亡災害・休業災害(4日以上): 「労働者死傷病報告(様式第23号または第24号)」を遅滞なく(死亡災害の場合)、または休業4日以上の場合には、休業初日を含まずに4日を経過した日、または負傷した日から14日以内に提出します。
- 休業1日~3日: 「労働者死傷病報告(様式第25号)」を四半期ごとに、まとめて提出します。
- 報告書の記載内容:
- 事故発生日時、場所、事故状況、負傷者の氏名、性別、年齢、所属部署、業務内容、負傷の部位・程度、災害の原因、再発防止策などを詳細に記載します。
- 虚偽の報告は厳に慎むべきです。
- 留意事項:
- 提出義務があるにもかかわらず報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合には、罰則(50万円以下の罰金など)が科せられる可能性があります。
- 労基署への報告は、労災保険の給付申請とは別の手続きです。
警察への届出(人身事故の場合)
労災によって人身事故が発生し、それが交通事故として扱われる可能性がある場合や、業務上過失致死傷罪に該当する可能性が疑われるような重大な事故の場合には、警察への届出が必要となる場合があります。
- 届出の判断基準:
- 公道上での事故である場合。
- フォークリフトやクレーンなどの車両系建設機械が関与し、死傷者が発生した場合。
- 明らかに業務上の過失が原因で、死亡または重傷を負わせた可能性がある場合。
- 事故の状況が、犯罪行為(業務上過失致死傷罪など)に該当するおそれがある場合。
- 届出方法:
- 110番通報または最寄りの警察署へ連絡し、事故状況を説明します。
- 警察による現場検証や関係者からの聞き取りが行われることがあります。
- 留意事項:
- 警察への届出は、刑事責任の追及に繋がる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
- 警察の捜査に協力し、事実を正確に伝えることが重要です。
- 弁護士に相談の上、対応を進めることを強く推奨します。
関係官庁・団体への報告
建設業においては、労基署や警察以外にも、事故の状況に応じて他の関係官庁や団体への報告が必要となる場合があります。
- 国土交通省:
- 建設業法に基づく特定建設工事の事故(死亡事故、重傷事故、特定機械の破損事故など)は、国土交通省(地方整備局)への報告が必要となる場合があります。これは、建設業法の監督処分の対象となり得るため、重要です。
- 都道府県・市町村:
- 公共工事における労災の場合、発注者である自治体への報告が求められます。契約書に記載された報告義務の内容を確認し、適切に対応する必要があります。
- 健康保険組合・年金事務所:
- 労災保険の適用となる労災であれば、基本的には健康保険や厚生年金保険は使用しませんが、万が一健康保険等で受診してしまった場合は、労災への切り替え手続きが必要となります。
- 関係する業界団体・協会:
- 所属している業界団体や協会によっては、労災発生時の報告が求められる場合があります。これは、情報共有や安全対策の取り組みの一環として行われるものです。
これらの報告義務を怠ると、企業としての信頼性が失われるだけでなく、事業運営に支障をきたす可能性もあります。どの機関に、どのような内容で報告すべきか迷う場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが賢明です。
企業が負う民事上の損害賠償責任とその負担を減らすためにできること
労災が発生した場合、企業は労働者に対する安全配慮義務を怠ったとして、被災者やその遺族から民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。これは、労災保険からの給付とは別に、企業が直接、被災者に支払うべき賠償金であり、その額は数千万から億単位に及ぶこともあります。
安全配慮義務違反と損害賠償責任
企業には、労働者が安全かつ健康に働けるよう、必要な措置を講じる義務があります。これを「安全配慮義務」と呼びます。具体的には、以下の項目が含まれます。
- 作業環境の整備: 危険な場所への囲い、足場の設置、墜落防止設備の設置など。
- 機械設備の安全確保: 定期的な点検、適切な保守管理、安全装置の設置など。
- 作業方法の指示: 危険作業手順の周知、安全作業マニュアルの作成と徹底など。
- 危険性情報の周知: 危険源の特定と注意喚起、リスクアセスメントの実施など。
- 教育訓練の実施: 安全衛生教育、特別教育、危険予知訓練など。
- 健康状態への配慮: 過重労働の防止、健康診断の実施、ストレスチェックなど。
労災が発生し、上記のような安全配慮義務を怠ったと判断された場合、企業は債務不履行(民法第415条)または不法行為(民法第709条)に基づき、被災者に対して損害賠償責任を負います。
損害賠償の対象となるもの:
- 治療費: 労災保険給付の対象とならない自由診療費用、将来の治療費など。
- 休業損害: 労災保険の休業補償給付ではカバーしきれない部分(通常は給付基礎日額の60%が給付されるため、残りの40%などが対象となる)。
- 逸失利益: 労災により労働能力を喪失または減退したことで、将来得られるはずだった収入の減少分。
- 慰謝料: 精神的苦痛に対する賠償。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など。
- 付添看護費用: 入院中や自宅療養中に必要となる介護費用。
- 葬儀費用: 死亡労災の場合。
これらの損害賠償額は、負傷の程度、後遺障害の有無、年齢、収入などによって大きく変動し、特に死亡事故や重度後遺障害が残る事故の場合、数千万円から1億円を超える高額な賠償となるケースも少なくありません。
損害賠償請求への対応
損害賠償請求を受けた場合、企業は適切な対応を取る必要があります。
- 事実関係の確認と証拠収集:
- 事故発生時の状況、安全対策の実施状況、被災者の過失の有無など、事実関係を詳細に確認します。
- 先に述べた証拠保全がここで活きてきます。写真、動画、作業記録、点検記録、関係者の証言などを整理し、企業側の主張を裏付ける証拠を収集します。
- 責任の有無と過失割合の検討:
- 企業に安全配慮義務違反があったか否か、また、あったとしてもどの程度の過失があったのかを検討します。
- 被災者側にも過失があった場合は、過失相殺により、企業が支払うべき損害賠償額を減額できる可能性があります(例:被災者が安全帯を着用していなかった、指示に従わなかったなど)。
- 損害額の算定:
- 被災者から請求された損害賠償額が適正なものであるか、法的な基準に基づいて精査します。過剰な請求に対しては、適切に反論する必要があります。
- 示談交渉:
- 訴訟に発展する前に、被災者側と示談交渉を行います。弁護士が代理人となって交渉を進めることで、感情的にならず、客観的な視点から冷静に話し合いを進めることができます。
- 示談が成立すれば、早期に紛争を解決し、企業のイメージダウンを最小限に抑えることができます。
- 訴訟対応:
- 示談交渉が不調に終わった場合、被災者側が訴訟を提起する可能性があります。
- 訴訟では、裁判所に証拠を提出し、法律的な主張を行うことになります。弁護士は、企業側の代理人として、法廷で弁論を行い、貴社の利益を最大限に守るために尽力します。
これらの対応は専門的な知識と経験を要するため、労災に詳しい弁護士に早期に相談することが不可欠です。
建設業特有の損害賠償責任(元請け・下請け間の責任関係)
建設業では、元請負業者と複数の下請負業者が混在して一つの現場で作業を行うことが一般的です。この複雑な構造が、労災発生時の責任関係をさらに複雑にしています。
- 元請負業者の責任:
- 元請負業者は、下請負業者やその労働者に対しても、現場全体の安全衛生を統括する責任を負います(労働安全衛生法第30条)。
- 下請負業者の労災であっても、元請負業者が安全管理義務を怠ったと判断されれば、元請負業者も損害賠償責任を負う可能性があります。
- 特に、元請負業者が現場の安全設備設置を怠っていた、危険な作業を指示していたなどの場合、重い責任が問われることがあります。
- 下請負業者の責任:
- 下請負業者も、自社の労働者に対して安全配慮義務を負います。
- 自社の労働者の労災については、基本的に下請負業者が第一次的に責任を負うことになります。
- 連帯責任:
- 元請負業者と下請負業者の双方が安全配慮義務違反を犯していた場合、両者が連帯して損害賠償責任を負うことがあります。この場合、被災者はどちらの企業に対しても全額の賠償を請求でき、請求を受けた企業は、もう一方の企業に対してその責任割合に応じた負担を求めることになります。
- 責任関係の複雑化:
- 多層構造になっている建設現場では、どこの企業が、どの範囲で安全配慮義務を負っていたのか、また、どの企業が原因で事故が発生したのかを特定することが非常に困難になる場合があります。
- このような状況では、弁護士による詳細な事実関係の調査と、各企業の責任範囲の明確化が不可欠です。
元請け・下請け間の責任関係は、法的に非常に複雑な問題を含みます。当事務所は、建設業における労災案件に精通しており、このような複雑な責任関係においても、貴社の利益を最大限に守るための戦略を立案し、対応をサポートいたします。
労災保険以外の企業防衛策
労災保険は、被災者の保護を目的とした公的保険であり、企業が民事上の損害賠償責任を負う際に、その全てをカバーするものではありません。労災保険からの給付だけでは不足する部分について、企業は直接賠償金を支払う義務が生じるため、労災保険以外の企業防衛策を講じることが重要です。
- 使用者賠償責任保険(任意労災保険)への加入:
- 労災保険の給付を超える部分の損害賠償責任に備えるための保険です。
- 近年、この保険への加入は建設業において必須とも言える状況になってきています。
- 万が一の労災事故で高額な賠償金を請求された場合でも、この保険があれば企業の財務的な打撃を大幅に軽減できます。
- 保険会社によって補償内容や保険料が異なるため、貴社の事業規模やリスクに応じた適切な保険を選択することが重要です。
- 安全管理体制の強化と定期的な見直し:
- 最も根本的な企業防衛策は、そもそも労災を発生させないことです。
- 労働安全衛生法遵守はもちろんのこと、リスクアセスメントの徹底、安全衛生教育の継続的な実施、作業手順の明確化、安全設備の定期的な点検・整備など、積極的な安全管理投資を行うことが、結果として企業の損失を防ぐことに繋がります。
- 安全管理体制は一度構築すれば終わりではなく、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回し、常に最新の状況に合わせて見直していく必要があります。
- 顧問弁護士との連携:
- 労災発生時の初動対応から、損害賠償請求への対応、再発防止策の検討に至るまで、法的な専門知識が必要となる場面は多岐にわたります。
- 日頃から顧問弁護士と連携しておくことで、労災が発生した際に迅速かつ適切なアドバイスを受けることができ、企業の損失を最小限に抑えることが可能になります。
- また、事前に安全管理体制について法的な観点からのチェックを受けることで、労災リスクを低減させることにも繋がります。
再発防止と安全管理体制の強化
労災が発生してしまった場合、最も重要なことは、二度と同じ過ちを繰り返さないために、徹底した再発防止策を講じることです。これは、被災者やその家族に対する企業の誠意を示すだけでなく、企業の社会的責任を果たす上でも不可欠です。
- 原因究明の徹底:
- 事故発生後、速やかに事故調査委員会などを設置し、専門家を含めて多角的に事故原因を究明します。
- 「なぜ事故が起きたのか?」だけでなく、「なぜ安全対策が機能しなかったのか?」「なぜ危険な状態が放置されていたのか?」といった根本原因(真因)まで掘り下げて分析することが重要です。
- ヒューマンエラーだけでなく、組織的な要因、管理体制の不備、教育訓練の不足など、複合的な要因を考慮に入れます。
- 改善策の策定と実施:
- 究明された原因に基づき、具体的な改善策を策定します。
- 技術的対策: 機械設備の改良、安全装置の導入、作業方法の変更など。
- 管理的対策: 安全衛生管理規程の見直し、リスクアセスメントの強化、作業標準の見直し、安全衛生委員会の活性化など。
- 教育的対策: 安全衛生教育の充実、危険予知訓練の徹底、OJTの強化など。
- 策定した改善策は、絵に描いた餅で終わらせず、具体的な実施計画を立て、責任者を明確にして確実に実行に移します。
- 安全管理体制の継続的な見直しと改善:
- 一度導入した安全管理体制も、時間の経過や環境の変化に伴い陳腐化する可能性があります。
- 定期的に安全管理体制の有効性を評価し、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことが重要です。
- ヒヤリハット活動の推進、安全パトロールの実施、安全衛生目標の設定と評価などを通じて、常に安全意識を高め、危険の芽を早期に摘み取る努力を続けます。
- 情報共有と意識改革:
- 労災事例やヒヤリハット事例を社内で共有し、再発防止策の重要性について、従業員一人ひとりの意識を高める取り組みが不可欠です。
- 経営トップから現場の作業員まで、全従業員が安全を最優先するという意識を共有することが、真の安全文化を醸成することに繋がります。
再発防止の取り組みは、企業の社会的責任を果たす上で不可欠であるだけでなく、長期的に見て企業の生産性向上やコスト削減、人材定着にも繋がる重要な投資です。
労災発生時の弁護士の役割とサポート内容
労災が発生した場合、企業は多岐にわたる複雑な問題に直面します。その際、法的な専門知識を持つ弁護士のサポートは、企業が適切な対応を取り、不必要なリスクを回避するために不可欠です。
労災発生時における弁護士の主な役割とサポート内容
- 初期対応に関するアドバイス:
- 事故発生直後の負傷者救護、現場保全、関係者への連絡など、初動段階での法的リスクを考慮した具体的なアドバイスを提供します。
- 証拠保全の重要性とその方法について指導し、後の紛争に備えるための準備をサポートします。
- 法令に基づく報告義務のサポート:
- 労働基準監督署、警察、その他関係官庁への報告義務の有無を判断し、適切な報告書作成を支援します。
- 報告内容が後の紛争に不利にならないよう、法的な観点から内容を精査します。
- 事故原因究明・責任関係の調査:
- 事故の原因究明に際し、客観的な第三者の視点から調査をサポートします。
- 元請け・下請け間の複雑な責任関係を法的に分析し、企業の責任範囲を明確にします。
- 被災者側の過失の有無など、損害賠償額に影響を与える可能性のある要素を徹底的に洗い出します。
- 損害賠償請求への対応:
- 被災者やその遺族からの損害賠償請求に対し、企業側の代理人として対応します。
- 請求された損害賠償額の適正性を検討し、過剰な請求に対しては法的な根拠に基づいて反論します。
- 示談交渉を主導し、企業の損失を最小限に抑えつつ、早期解決を図ります。
- 交渉が不調に終わった場合は、訴訟代理人として、企業側の主張を裁判所に提出し、貴社の権利を擁護します。
- 労働基準監督署の調査・警察の捜査への対応:
- 労基署や警察からの聴取、立ち入り検査などに対し、企業としてどのように対応すべきか、具体的なアドバイスを提供します。
- 必要に応じて、弁護士が立ち会い、企業の権利が不当に侵害されないようサポートします。
- 再発防止策の法的チェック:
- 策定された再発防止策が、法的な要件を満たしているか、また、実効性のあるものであるかについて、弁護士の視点から検証し、アドバイスを提供します。
- 安全衛生管理規程の見直しなど、安全管理体制の改善をサポートします。
- 風評被害対策:
- 労災発生により企業イメージが損なわれることを防ぐため、適切な情報開示の仕方や、メディア対応についてアドバイスします。
弁護士は、単に法律問題に対処するだけでなく、企業のブランドイメージを守り、事業継続を支援するパートナーとして機能します。特に、労災は突発的に発生し、企業を窮地に陥れる可能性のある重大な危機です。そのため、日頃から労災問題に強い弁護士と顧問契約を結んでおくことが、最大の「企業防衛策」となるのです。
当事務所のサポート内容
リブラ法律事務所は、建設業界の特性と労災問題の複雑さを深く理解しております。当事務所は、地域の中小企業の皆様の身近な法律パートナーとして、労災に関するあらゆるお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。
リブラ法律事務所が提供する労災対応サポートの主な内容
- 労災発生時の緊急初動サポート
- 事故発生直後から、電話やオンライン会議を通じて迅速に状況を把握し、負傷者救護、現場保全、証拠収集、関係機関への速報など、初動段階での具体的な指示と法的アドバイスを提供します。
- 弁護士が現場に急行し、状況を確認することも可能です(別途費用)。
- 労働基準監督署・警察等への報告書類作成支援・提出代行
- 「労働者死傷病報告」をはじめとする各種報告書の作成を支援し、適切な内容で提出できるようサポートします。
- 必要に応じて、弁護士名義での報告書提出や、監督署・警察からの聞き取りへの立ち会いも行い、貴社の法的利益を守ります。
- 事故原因調査・責任関係の法務支援
- 第三者の目線から、客観的な事故原因の調査を支援します。
- 元請け・下請け間の複雑な契約関係や安全管理体制を精査し、法的責任の所在と範囲を明確にします。
- 貴社側に有利な証拠の収集方法や、不利な証拠への対応策についてアドバイスします。
- 損害賠償請求対応(示談交渉・訴訟対応)
- 被災者やその遺族からの損害賠償請求に対し、貴社の代理人として粘り強く交渉を行います。
- 請求額の適正性を厳しく精査し、過失相殺や損害額の減額交渉など、貴社の負担を最小限に抑えるための戦略を実行します。
- 示談での解決が困難な場合は、訴訟代理人として貴社を全面的にサポートし、法廷で貴社の主張を力強く展開します。
- 労災保険・使用者賠償責任保険に関するアドバイス
- 労災保険の給付申請プロセスに関する一般的なアドバイスや、使用者賠償責任保険の活用方法について、貴社の状況に応じて具体的な助言を行います。
- 再発防止策・安全管理体制強化への法的助言
- 労災発生後に策定する再発防止策や、既存の安全管理体制について、労働安全衛生法などの法令遵守の観点から法的チェックを行い、より実効性の高い安全体制構築をサポートします。
- 社内規程の整備や安全衛生教育プログラムの見直しなども支援します。
- 危機管理・情報公開に関するサポート:
- 労災発生時の社内外への情報公開、メディア対応など、企業のレピュテーションを守るための危機管理戦略についてアドバイスします。
中小企業の社長様へ
建設業における労災は、貴社の事業を揺るがす重大なリスクです。しかし、日頃から適切な備えをし、万が一の事態に際して弁護士の専門知識を活用することで、そのリスクを最小限に抑えることができます。
「労災が起きてからでは遅い」という言葉の通り、事前の備えと、初動段階での迅速かつ適切な対応が、企業の命運を分けると言っても過言ではありません。当事務所は、貴社が安心して事業を継続できるよう、労災に関するあらゆる問題に対し、法律の専門家として全力でサポートいたします。
労災問題は、ただでさえ複雑な建設現場の状況に、さらに法的・行政的な複雑さを加えます。貴社が本業に集中できるよう、労災対応に関する重荷は、ぜひ当事務所にお任せください。
労災に関するご相談は、初回無料で承っております。まずはお気軽にお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。貴社のお困り事を丁寧にヒアリングし、最適なサポートプランをご提案させていただきます。
リブラ法律事務所は、貴社の頼れるパートナーとして、建設業の健全な発展を法的に支援いたします。
お問い合わせはこちら
- 電話番号:097-538-7720
- お問い合わせフォーム:https://kigyo-lybralaw.com/contact
▼関連記事はこちら▼
【実践ガイド2025】「泣き寝入りはもう終わり!建設業のための【未払い工事代金】改修マニュアル」
建設請負工事における契約不適合責任と損害賠償について弁護士が解説
建設業でよくある労務問題とは?残業代請求などに打ち手弁護士が解説!
建設業の方へ-発注者からのクレーム(カスハラ)・発注者とのトラブルの対応とは?-
施主の工事代金未払いの回収方法とは?建設会社の債権回収にポイントについて弁護士が解説
Last Updated on 7月 9, 2025 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |





