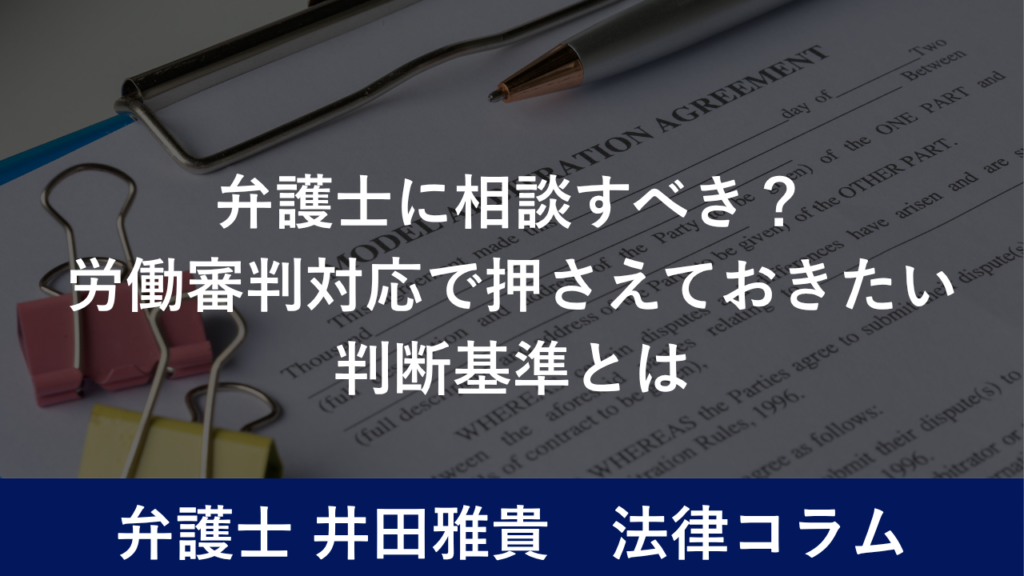
突然、従業員から労働審判を申し立てられた——。
そんな状況に直面した経営者や人事担当者の多くは、「弁護士に依頼すべきか」「自社で対応できるのか」という判断に迷われることでしょう。労働審判は原則3回以内、平均81日で終結する迅速な手続きですが、だからこそ初動対応が極めて重要です。
本記事では、労働審判における企業対応の重要性から、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリット、さらには弁護士を選ぶ際のチェックポイントまで、企業の労働審判対応に必要な判断基準を詳しく解説します。
1.労働審判における「企業対応」の重要性とは
労働審判制度の基本構造
労働審判は、労働者と使用者間の個別労働関係紛争を迅速・適正に解決するため、2006年4月に導入された制度です。労働審判官(裁判官)1名と労働審判員(民間専門家)2名で構成される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理を行います。
令和5年の司法統計によると、労働審判の新受件数は全国で3,473件。このうち約69.4%が調停による和解で終了しており、企業にとっては交渉による解決が現実的な選択肢となっています。
企業側が直面する時間的制約
労働審判における企業側の最大の特徴は、極めて短い準備期間です。申立書を受領してから第1回期日まで原則40日以内、答弁書の提出期限はその約1週間前に設定されます。
つまり、企業は約1ヶ月という限られた時間で以下の対応を完了させる必要があります:
- 申立内容の法的分析
- 事実関係の調査・整理
- 証拠書類の収集
- 答弁書の作成・提出
- 第1回期日への出廷準備
一方で労働者側は、申立て前に十分な準備期間を確保しているため、企業側は「準備格差」という不利な状況からスタートすることになります。
第1回期日の決定的重要性
労働審判では第1回期日での印象形成が極めて重要です。労働審判委員会は、提出された申立書と答弁書を事前に検討し、第1回期日で両当事者への質問を通じて心証を形成します。
実際の統計を見ると、70%の事件が2回以内で終結しており、第1回期日での労働審判委員会の心証が最終的な解決内容に大きく影響することが分かります。
この「一発勝負」的な性格こそが、労働審判における企業対応の重要性を際立たせているのです。
2.弁護士に依頼することで得られる5つの実務的メリット
法的主張の構成力
労働法の専門的解釈
労働審判では、労働基準法、労働契約法、民法など複数の法律が複雑に絡み合います。例えば、解雇事案では「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」という労働契約法16条の要件を、具体的事実に基づいて立証する必要があります。
経験豊富な弁護士であれば、類似判例を踏まえた法的主張を構築し、企業に有利な解釈を提示できます。
戦略的な論点整理
労働審判委員会は、争点を絞り込んで迅速な解決を図ろうとします。弁護士は、多数の争点の中から企業に有利な争点を前面に押し出し、不利な争点を後退させる戦略的な主張構成を行います。
実際のケースでは、残業代請求事案において、金額の算定よりも「そもそも残業の事実があったか」という前提事実に焦点を当てることで、企業側の主張を通した事例もあります。
証拠の収集と整理
効果的な証拠戦略
労働審判では限られた期日で結論を出すため、決定的な証拠の提出が勝敗を分けます。弁護士は以下のような観点から証拠を戦略的に収集・整理します:
解雇事案での証拠例:
- 就業規則、雇用契約書
- 懲戒処分の根拠となる事実を示す資料
- 注意指導の記録、人事評価
- 同僚の証言書
- 業務日報、メール履歴
残業代請求での証拠例:
- タイムカード、PCログ、入退室記録
- 業務指示書、残業命令書
- 36協定、就業規則の労働時間規定
- 給与規定、割増賃金の支払実績
証拠能力の判断
単に証拠を集めるだけでなく、どの証拠が労働審判委員会の心証形成に効果的かを判断する能力が重要です。弁護士は、証拠の証明力や相手方の反論可能性を考慮して、最も説得力のある証拠を選別・提出します。
期日対応と質問対策
労働審判委員会との効果的なコミュニケーション
第1回期日では、労働審判委員会から企業の担当者に対して直接質問が行われます。この質問対応如何で企業への印象が大きく左右されるため、事前の準備が欠かせません。
弁護士は以下のような質問対策を行います:
想定質問例と対応方針:
- 「なぜこの従業員を解雇したのか」→ 客観的事実に基づく説明
- 「残業の指示はしていたのか」→ 業務の必要性と指示の有無を明確化
- 「改善の機会は与えたのか」→ 指導・教育の実施状況を具体的に説明
感情的対立の回避
労働審判では、企業と労働者が同じテーブルで対面することになります。感情的な対立が生じやすい状況ですが、弁護士が間に入ることで冷静で建設的な議論を維持できます。
実際に、企業担当者が感情的になって不適切な発言をしてしまい、労働審判委員会の心証を悪化させた事例もあります。弁護士がいることで、このようなリスクを回避できます。
企業の負担軽減
業務継続への配慮
労働審判対応は、企業の通常業務と並行して進める必要があります。弁護士に依頼することで、以下の業務負担を軽減できます:
- 書面作成業務:答弁書、準備書面の作成
- 証拠収集業務:関係資料の整理、証人との調整
- 期日対応業務:裁判所への出廷、交渉対応
- 進行管理業務:期限管理、相手方との連絡調整
専門知識不足によるリスク回避
労働法は専門性が高く、判例の蓄積も膨大です。企業が自社対応を試みた結果、法的に不適切な主張をして敗訴リスクを高めるケースも少なくありません。
弁護士への依頼は、このような専門知識不足によるリスクを根本的に解決します。
調停・和解における交渉力
適正な解決金額の算定
労働審判の約7割が調停による和解で終了することから、解決金額の交渉が極めて重要です。弁護士は以下の要素を総合的に検討して、適正な解決水準を算定します:
解決金算定の考慮要素:
- 法的に認められる請求額の上限
- 企業側の反論可能性と勝訴見込み
- 訴訟移行した場合の費用・時間
- 企業の経営状況と支払能力
- 風評リスクや従業員への影響
有利な和解条件の獲得
解決金額だけでなく、和解条件の設定も重要です。経験豊富な弁護士であれば、以下のような企業に有利な条件を盛り込むことができます:
- 守秘義務条項:紛争内容の口外禁止
- 蒸し返し防止条項:追加請求の放棄
- 風評対策条項:SNS等での誹謗中傷禁止
- 迷惑行為禁止条項:元従業員の業務妨害防止
交渉タイミングの見極め
労働審判では、第1回期日での心証形成を受けて第2回、第3回期日で調停による解決が図られます。弁護士は労働審判委員会の心証を正確に読み取り、最適な交渉タイミングを見極めて和解交渉を進めます。
3.弁護士に依頼しないと起こりがちなトラブルと敗訴リスク
準備不足による不利な心証形成
答弁書の質的問題
自社作成の答弁書でよく見られる問題点:
法的根拠の不明確さ
- 「解雇は正当だった」という結論のみで、労働契約法16条の要件に沿った主張ができていない
- 判例や通達への言及がなく、説得力に欠ける
事実と法的評価の混同
- 感情的な表現や主観的な評価が混入
- 客観的事実の整理ができていない
構成の不適切さ
- 争点が整理されておらず、主張が散漫
- 重要な論点が埋もれてしまう
証拠の不適切な選択
企業が自社対応した際によく起こる証拠提出の問題:
- 決定的証拠の見落とし:存在していたのに気づかない
- 不利な証拠の提出:相手方の主張を補強してしまう
- 証拠の整理不足:膨大な資料を整理せずに提出し、要点が不明確
期日対応での致命的ミス
不適切な発言による心証悪化
実際に企業担当者が陥りがちな発言例:
- 感情的な表現:「あの従業員はとんでもない問題社員だった」
- 法的理解の不足:「労働基準法違反ではない」(根拠なし)
- 矛盾した説明:事前の主張と期日での説明が食い違う
質問対応の準備不足
労働審判委員会からの質問に対して:
- 即答できずに曖昧な回答
- 事実関係を正確に把握していない
- 証拠との整合性が取れない説明
和解交渉での判断ミス
解決金額の相場感の欠如
弁護士なしで和解交渉を進めた企業が陥りがちな問題:
- 過大な解決金での和解:法的根拠のない高額な要求を受け入れ
- 不適切な条件の受諾:将来的なトラブルの火種となる条件での合意
- 交渉タイミングの誤り:有利な状況での早期妥結や、劣勢での強硬姿勢
二次被害の発生
適切な和解条件を設定しなかった結果:
- 他の従業員への波及効果
- 類似事案の続発
- 企業の労務管理に対する信頼失墜
訴訟移行時の不利益
労働審判で異議申立てされて訴訟に移行した場合、準備不足の企業は:
- 既に不利な記録が作成されている
- 相手方に手の内を知られている
- 追加準備の時間・費用が発生
結果として、最初から弁護士に依頼していれば回避できた敗訴リスクを抱えることになります。
4.弁護士を選ぶ際のチェックポイントと相談のタイミング
専門性の確認ポイント
労働法務の専門性
労働審判対応の弁護士選びで最も重要なのは、労働法務の専門性と実務経験です。以下の観点で確認しましょう:
専門性の確認項目:
- 労働審判の代理人経験(申立て側・相手方側双方の経験)
- 企業側労働法務の取扱実績
- 労働関係の論文・講演実績
- 労働委員会での経験
企業側対応の経験
労働問題を扱う弁護士の中には、労働者側専門の弁護士も多数存在します。企業側の立場を理解し、企業の利益を最大化する観点で対応できる弁護士を選ぶことが重要です。
企業側経験の確認方法:
- 顧問先企業数と業種
- 企業法務全般の取扱実績
- 人事労務制度の構築支援経験
- 社会保険労務士等との連携体制
対応力の見極め方
迅速性への対応力
労働審判は時間との勝負です。以下の点で弁護士の対応力を確認しましょう:
- 初回相談から受任までのスピード
- 連絡の取りやすさ(緊急時の対応体制)
- 期限管理の確実性
- チーム体制の有無(複数の弁護士による対応)
コミュニケーション能力
企業の実情を正確に理解し、労働審判委員会に効果的に伝える能力:
- 業界知識の深さ
- 説明の分かりやすさ
- 質問に対する的確な回答
- 企業の方針との整合性
費用の透明性
明確な料金体系
労働審判対応の弁護士費用は事務所によって差があります。以下の点を事前に確認しましょう:
確認すべき費用項目:
- 着手金:事件受任時の費用
- 報酬金:成功度合いに応じた費用
- 実費:交通費、印紙代等
- 日当:出廷に伴う費用
費用対効果の検討
弁護士費用と期待できる効果(解決金の減額等)を比較検討し、経済合理性を確認することも重要です。
5.相談タイミングの重要性
申立書受領後すぐに相談
労働審判申立書を受領したら、可能な限り早期に弁護士に相談することをお勧めします。理想的には受領から48時間以内の相談が望ましいでしょう。
早期相談のメリット:
- 十分な準備時間の確保
- 戦略的な対応方針の策定
- 証拠保全の適切な実施
- 企業内での情報共有体制の構築
予防的相談の効果
労働審判を申し立てられる前の段階、例えば従業員とのトラブルが発生した時点で弁護士に相談することで、より効果的な対応が可能になります:
- トラブルの予防・早期解決
- 適切な労務管理体制の構築
- 証拠の適切な収集・保管
- 従業員への対応方針の策定
6.リブラ法律事務所のサポート内容
企業法務に特化した専門サービス
弁護士法人リブラ法律事務所は、代表の井田雅貴弁護士を中心に、中小企業の法的課題解決に特化したサービスを提供しています。労働審判対応においても、企業の立場に立った戦略的なサポートを行います。
労働審判対応の特色
迅速な初期対応 申立書受領から答弁書提出まで、限られた時間の中で効率的に対応します。井田弁護士は「顧客との『リズム』や『テンポ』を大事にしている」として、企業の緊急性に応じた迅速なサポートを重視しています。
他士業との連携 社会保険労務士、税理士等との連携により、労務管理の改善から税務上の問題まで、ワンストップでの解決を図ります。労働審判をきっかけに、企業の労務管理体制全体を見直すサポートも提供可能です。
具体的なサービス内容
労働審判代理業務
- 申立内容の法的分析と対応方針の策定
- 答弁書・準備書面の作成
- 証拠収集・整理の支援
- 労働審判期日への出席・交渉
- 和解条件の検討・交渉
予防法務サービス
- 就業規則の見直し・改定
- 労働契約書のリーガルチェック
- 人事制度の法的適正性の検証
- 労務管理に関する定期的な相談
大分地域の企業に密着したサポート
地域密着の強み
大分県に根ざした法律事務所として、地域企業の実情を深く理解したサポートを提供します。地域の労働慣行や業界特性を踏まえた実践的なアドバイスが可能です。
アクセスの良さ
大分市中島中央に位置し、専用駐車場も完備。JR大分駅からタクシーで約10分、バス停「六条」から徒歩約3分と、企業の皆様にとってアクセスしやすい立地です。
7.相談から解決までの流れ
1. 初回相談(緊急対応可能) 労働審判申立書の内容確認と緊急性の判断を行います。
2. 受任・方針決定 企業の方針と法的リスクを総合的に検討し、対応戦略を策定します。
3. 答弁書作成・提出 期限内に説得力のある答弁書を作成・提出します。
4. 期日対応 労働審判期日に同行し、効果的な主張・交渉を行います。
5. 解決・アフターフォロー 和解成立後も、類似トラブルの予防策についてアドバイスします。
8.まとめ
労働審判は、その迅速性ゆえに初動対応が極めて重要な手続きです。企業が自社対応を選択することも法的には可能ですが、限られた準備期間の中で専門的な対応を求められることから、弁護士への依頼を強くお勧めします。
特に以下の要素がある場合は、弁護士依頼は必須と考えるべきでしょう:
- 請求金額が高額(100万円以上)
- 法的論点が複雑(解雇の有効性、労働時間の認定等)
- 企業の信用・評判への影響が大きい
- 他の従業員への波及効果が懸念される
労働審判申立書を受領された企業の皆様は、まず専門家である弁護士にご相談いただき、適切な対応方針を検討されることをお勧めします。早期の対応が、最終的な解決内容を大きく左右することを念頭に、戦略的なアプローチを心がけましょう。
弁護士法人リブラ法律事務所では、企業の皆様の労働審判対応を全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
9.ご予約・お問い合わせ
弁護士法人リブラ法律事務所 〒870-0049 大分県大分市中島中央2丁目2番2号 TEL: 097-538-7720(受付時間:平日9:00-18:00 ※12:00-13:00除く)
労働審判は時間との勝負です。申立書が届いたら、まずはお電話でご予約ください。経験豊富な弁護士が、貴社の立場に立って全力でサポートいたします。
▼関連記事はこちら▼
労働審判対応を弁護士に依頼するメリット 大分市の経営者・人事担当者向け完全ガイド
労働審判で不当解雇を主張された場合の会社側の対応について弁護士が解説
Last Updated on 11月 13, 2025 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |





