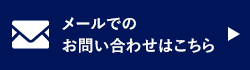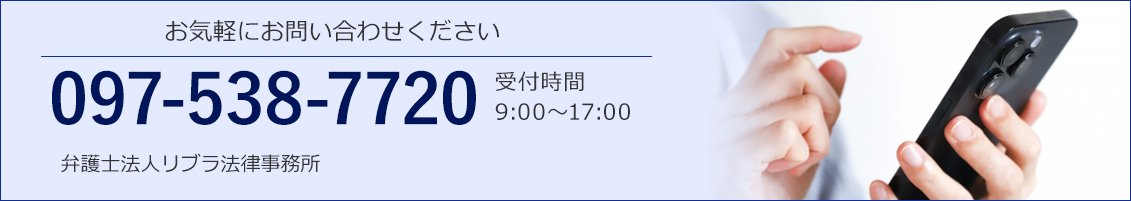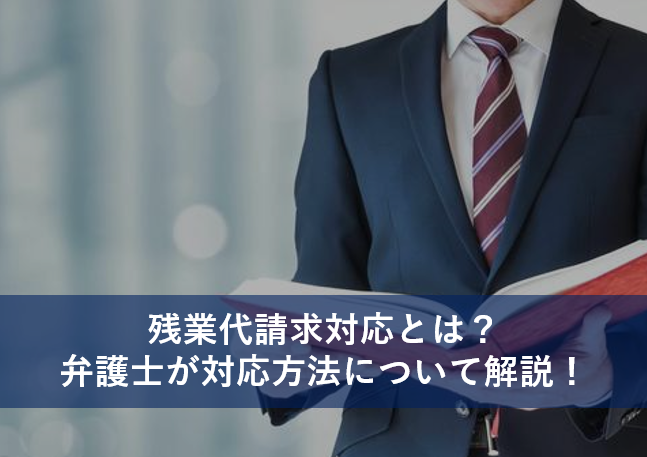
残業代請求対応とは?
従業員による事業者に対する残業代請求は、労働問題の中で最も頻繁に起こる問題で、かつ、事業者にとっては深刻な問題です。というのも、年間の事業予算で全く予定していない金銭、しかも高額の金銭の支払い余儀なくされる可能性があるからです。労働基準法は、使用者に対して従業員の労働時間を制限し、時間外労働については割増賃金の支払義務を課しています(労基法32条、36条、37条、119条等)。このため、事業者は労働者に対して、ルールに則って労働時間を管理し、時間外労働については通常労働の時給等に割増しをした金銭を支払うこととしています。
事業者が、漠然と労働者を働かせていると、思わぬ残業代を請求されます。従業員の時間外労働や休日労働は行き過ぎないように配慮し、今の給与体系や就業規則の定めを絶えず確認していただくことが、予期せぬ残業代請求を防ぐことになります。
事業者がルールを守って初めて従業員に残業をしてもらうことができます
事業者の皆様もご承知の通り、労働基準法は、使用者が従業員に労働させることができる1週および1日の最長労働時間を、それぞれ、40時間・8時間と定めています(法定労働時間といいます、労基法32条1項、2項)。
また「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定めており、週休制が基本です(労基法35条1項)。つまり、法律上、事業者が労働者を働かせることができる時間には制約があります。
事業者が労働者に対して、法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働を行わってもらいたいときには、いわゆる36協定の締結はもちろん、就業規則にも、「使用者は労働者に対し、業務上の必要があるときは残業を命じることができる」との定めを明記しておく必要があります。
つまり、従業員に残業を命じるためにはルールを設定することが必要です。
働き方改革の内容とは?-従業員に「(できる限り)残業させない」ことが求められます-
むしろ、従業員に「(できる限り)残業させない」ことが求められます。
事業者の皆様もご承知のとおり、いわゆる働き方改革により、残業時間について上限が設けられました。下記のとおりです。
残業時間の規制は、事業規模に関係なくすべての事業者に適用されます。
・残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。
・原則である月45時間を超えられるのは年間6か月までです。
・月60時間を超える残業時間については、割増賃金率が引き上げられる
▼関連記事はこちらから▼
物流・運送業界の2024年問題への対処法とは?弁護士が徹底解説!
運送業界の2024年問題とは?-想定されるトラブルについて弁護士が解説!-
昔は「サービス残業」の名の下、本来は残業代を支払わないといけない場合でも、従業員が遠慮して請求しなかったという事態がよく見られました。
しかし、今は令和です。昔の労働慣行は通用しません。社会で法令順守という意識が高まり、「ブラック企業」という言葉が完全に市民権を得た現代社会では、「日ごろから従業員によくしているから残業代は請求しないだろう」という甘い見込みで対応することは事業を危うくします。
しかも、残業代請求は、3年間遡って請求され、将来的には、これを5年遡れるようにする法改正も十分考えられます(むしろ、そう改正する方が他の法律とのバランスがとれるのです)。このため、現代の事業者は、従業員をいかに残業させないか、を考える必要があります。
事業者が、従業員を安易に残業させないよう社内体制を構築することは、事業者側からの不満の種である「何となく働く従業員にも残業代を支払わないといけないのか」(俗な言い方をすると「仕事ができない者ほど残業代を沢山受け取るのはおかしい」ということです。)という事態を阻止することに繋がります。つまり、事業者が、所定労働と時間外労働の線引き明確にしていくことになるのです。
少なくとも、労働時間はタイムカード等で厳格に管理すること、従業員からの残業申請は上司が承認した場合にのみ認める、という規定は就業規則で制定した方がいいといえます。
残業代請求はまずは弁護士にご相談ください-「うちは残業手当を支払っているから大丈夫」という事業者様へ-
定額・固定残業代を支払っているからといって安心できません。当然ですが、従業員に支払う定額残業代が、その労働者が実際に残業した時間によって計算される残業代に満たないのであれば、事業者が定額残業代との差額を請求されても文句はいえません。そればかりか、事業者が定額残業代を支払っている「つもり」であっても、裁判所がその支払いを残業代に対する支払いとして認めないことすらあります。定額残業代とさえ名称を付ければ足りるものではありません。残業代を巡る民事裁判では、法的に細かい論点が沢山ありますが、事業者の皆様が、裁判例を熟知していることは少なく、私たちの目から見れば、その支払い方法は問題がある、という支払いをなしている事業者が多いのが実態です。とにかく、残業代については、法律自体が変わることもあれば、裁判例での取扱いが代わることもあります。おまけに、「その労働が残業といえるか」「その休憩時間は休憩といえるか(労働ではないか)」等と、事業所における休憩時間や労働への準備によって、従業員が主張する残業時間と事業者がいう残業時間が異なる、ということすらあります。つまり、事業者が就業規則を定め、36協定を締結するだけでは、事業者が予期しない残業代の発生を防ぐのに十分ではありません。従業員の労働を実際に管理することがとても重要なのです。労働規制は複雑なうえに、事業者側に残業代に関する誤解があれば、予期せぬ残業代が何百万円単位で発生することは決していい過ぎではありません。労務管理については、労働問題に強い弁護士や法律事務所などの労務の専門家の支援を受けることを強くお勧めいたします。
Last Updated on 1月 15, 2024 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |