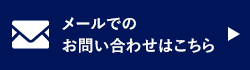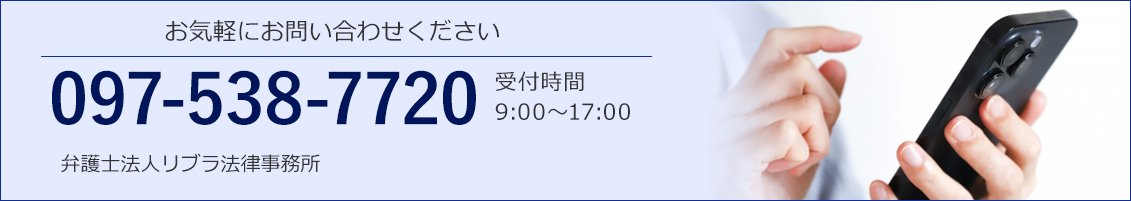企業は、労災の発生を防止すべき立場にあり、ひとたび労災が発生すると労働基準監督署から指導されたり、従業員側から損害賠償を請求されうる立場になります。この原稿では、労災について詳しく説明します。

0.はじめに
労災とは、労働者が仕事や通勤が原因で、負傷したり、病気になったり、亡くなったりすることです。身体的な怪我だけでなく、長時間労働やパワハラを原因とする精神疾患、長時間労働による過労死や自死も労災の1種です。
労働者は、労働基準監督署が労災を認定した場合、労災保険から補償を受けることができます。
労働者は、労災認定によりどのような給付を受けられるかについてはこちらの記事をご参照ください。
▼関連記事はこちらから▼
会社の労災対応・安全配慮義務について!-労災保険への加入・損害賠償での企業リスクとは?-
1.労災の種類
(1)業務災害
労働者が、業務が原因で、負傷、疾病、死亡することです。具体的には
・仕事中に機械に巻き込まれて怪我をした
・高所での作業中に転落して死亡した
という例です。
労働基準監督署は、労働者の怪我等が業務災害によるものと認定する際、業務と怪我等との間に相当因果関係があるかどうかを確認します。相当因果関係があれば労災を認定するのです。労働基準監督署は、業務と怪我等との因果関係の有無を「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要素で判断します。
<業務遂行性>
業務遂行性とは、「負傷や死亡等が業務中に発生したこと」です。業務中とは、労働者が労働契約に基づいて事業者の支配・管理下にある状態のことです。業務中とは「就業中」に限らず、事業主の支配ないし管理下にある中で災害が起きた場合も該当します。たとえば
・就業中でなくても、始業前、休憩中、終業後に起きた社内での事故
・出張の際の移動中や宿泊場所での事故
・事業活動に密接に関連した歓送迎会、忘年会、運動会、社員旅行等
における事故も業務中に含まれます。
<業務起因性>
業務起因性とは、「業務が原因で負傷や死亡等が発生したこと」です。業務が原因か否かはケースバイケースの判断ですが、大まかには、下記のとおり類型化できます。
・就業中の事故による災害
通常は、業務起因性が認められます。ただし、地震や落雷、業務とは無関係な事件(通り魔的犯行)の場合は、業務起因性が否定されることもあります。
・始業前、休憩中、終業後などに起きた社内での災害の場合
業務と関連する災害や、社内施設の不備による災害は、業務起因性が認められます。ただし、休憩中のスポーツでの負傷は、通常、業務起因性があるとはいえません。
・社外で就業中や出張中の災害
社外での就業や出張中の災害は、社内での就業よりも危険にさらされる範囲が広く、業務起因性が認められやすいです。例えば、出張先の宿泊施設で酔って階段から転落したという事故についても業務起因性が認められたケースがあります。
(2)通勤災害
労働者が、通勤の際に怪我をしたり亡くなったりすることです。通勤中に交通事故に遭うケースが典型的です。労働者が、会社に届け出ているものとは違う通勤経路や通勤方法の過程で怪我等をした場合でも、その経路や方法が、労働者が用いるものとして合理的である場合、使用者の業務命令を遂行するために係る経路や通勤方法に依拠した場合は「通勤」となります。ただし、仕事と関係のない目的で通勤経路から外れて負傷をした場合等は「通勤」中の災害と認定されません。
2,労災保険とは?
労災保険とは、仕事や通勤によって労働者が負傷したり、病気になったり、死亡したりした場合に、労働者やその遺族に対して、国が保険給付を行う制度です。
(1)労災保険の加入条件
事業主は、従業員を1人でも雇っている場合に加入する義務があります。雇用形態にかかわらず、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員、日雇い労働者等のすべての労働者が労災保険の加入対象者です。
(2)労災保険料は全額事業主の負担
事業主は、労災保険の保険料を全額負担します。
(3)事業主が未加入でも労災保険が使える
事業主が加入手続きをしていなかった場合や、労災保険料を滞納していた場合でも、労働者は、労災保険から補償を受けることが可能です。事業主は、この場合「追徴金の徴収」や「労災保険給付額の全額または一部の徴収」といった制裁を科せられます。このため、労災保険の利用を嫌がる事業主がいることも事実なのですが、褒められた対応ではありません。
(4)労災保険の特別加入制度とは?
労働者以外でも、例外的に、一定の条件を満たすことで労災保険に加入できます。労災保険の特別加入制度です。この特別加入制度の対象となる者は下記のとおりです。
・中小企業の経営者
・中小企業の役員
・一人親方
・個人事業主
・農業従事者
厚生労働省のホームページ等で、特別加入の申請書等の様式をダウンロードできます。必要な場合はアクセスしてください。
▼関連記事はこちらから▼
(5)労災保険と健康保険の違い
労災保険は仕事や通勤が原因のけがや病気等が補償の対象です。健康保険は業務外のけがや病気等が補償の対象です。補償の対象が異なるため、2つの保険は併用できません。労災であるにもかかわらず健康保険を使ってしまった場合は、労災保険へ切り替える手続が必要です。
(6)労災保険料のメリット制とは?
事業主が支払うべき労災保険料を計算する際、保険料率が予め決まっています。メリット制とは、この保険料率を、労災事故の発生件数に応じて上下させるものです。メリット制が適用されると、労災事故の発生件数が多い事業場は保険料が高く、労災事故の発生件数が少ない事業場は保険料が安くなります。こういう制度があるので、労災保険の利用を嫌がる事業主が存在するのです。もっとも、メリット制が適用されるのは、下記2つの要件を満たす事業者に限られます。
・労災保険に加入してから3年以上経過していること
・100人以上の労働者を雇用している
または、20人以上100人未満の労働者を雇用していて災害度係数が0.4以上であること
3.労災はどういう場合に認定されるか
(1)怪我や死亡の場合
労災事故による怪我や死亡の場合は、業務遂行性と業務起因性があれば労災(労働災害)に認定されます。事故状況という客観的状況で判断されやすいため、事業者にとっても労災該当性は予測可能かと存じます。
(2)うつ病や精神疾患の場合
業務起因性が認められれば、精神疾患も労災となりえます。パワハラや長時間労働が原因でうつ病となった、というのが具体例です。 もっとも、精神疾患は業務起因性の判断が上記(1)に比べて容易ではないため、3つの要件を満たす場合に限って労災が認定されます。
・発症前おおむね6か月以内に業務による強いストレスを受けたこと
・うつ病やストレス反応など労災認定の対象となる精神疾患と診断されたこと
・業務外のストレスや個体側要因により発症したとはいえないこと
厚生労働省は、令和5年、1つ目の要件に関する指針を改訂しました。
内容を確認したい場合は下記の原稿をご参照ください。
▼関連記事はこちらから▼
「発症前おおむね6か月以内に業務による強いストレスを受けた」とは?令和5年に改訂された指針のご紹介いたします
(3)腰痛の場合
介護事業に従事されている労働者や運送事業に従事しているドライバーによくみられる労災です。腰痛が生じた過程に着目して、労災認定の要件を区別しています。
<突発的で急激な強い力が原因となって生じた腰痛>
下記2つの要件を満たす場合に労災認定されます。
・原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
・腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
<日々の業務による腰への負荷が徐々に作用して発症した腰痛>
・突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められる場合
この基準に鑑みれば、ぎっくり腰は、日常的な動作のなかで生じるため、原則として、労災補償の対象にはなりません。
(4)脳・心臓疾患の場合
脳疾患(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血)や心臓疾患(心筋梗塞、狭心症)は、発症の原因が、「業務による明らかな過重負荷によるもの」である場合に労災認定されます。
ここで「業務による明らかな荷重負荷」とは
・発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす時に過重な業務に就労した場合
・発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労した場合
・発症直前から前日までの間において、精神的または身体的に強い負荷のかかる事態や急激な作業環境の変化等の異常な出来事に遭遇した場合
のいずれかのケースをいいます。
4,労災請求と凡その期間
労働者が労働基準監督署に請求書を提出した後、保険給付が決定するまでの期間は、概ね以下のとおりです。
・療養補償給付と休業補償給付の場合:おおむね1ヶ月
・障害補償給付の場合:おおむね3ヶ月
・遺族補償給付の場合:おおむね4ヵ月
労働者が労災の請求をして不支給となった場合や、給付の内容に不服がある場合は、不服申立てが可能です。もっとも、不服申立ての相手方は労働基準監督署(国)であるため、事業主が対処を求められるものではありません。
5.企業にとって労災発生後から専門家が関与することは必須です
労働者は、労災の請求を企業ではなく労働基準監督署に行います。
企業は、労働者の損害が全て労災で賄えると誤解することがあります。しかし、労災給付で労働者に生じた損害の全てをカバーできるわけではなく、後日、企業に対して別途損害賠償請求をしてくることがありえます。その場合に、労災段階で労働者に迎合するような対応(例えば、企業に責任があることを認めたり、実際には曖昧であるのに労働者に有利な事実があると認めること)をしていると、後の訴訟となった場合に、係る対応を修正することはできません。このため、労働者がなす労災請求の書類への記載や労働基準監督署に企業としての意見を表明しておくことは重要です。こうしてみると、労働者が労災請求を希望した時点で、労災事案を複数経験している弁護士に相談することは大事です。リブラ法律事務所では、労災が生じた場合に企業側がとるべき行動や労働基準監督署からの指導に対する対処方法等を助言することができます。お気軽にご相談ください。
▼関連記事はこちらから▼
Last Updated on 12月 22, 2023 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |