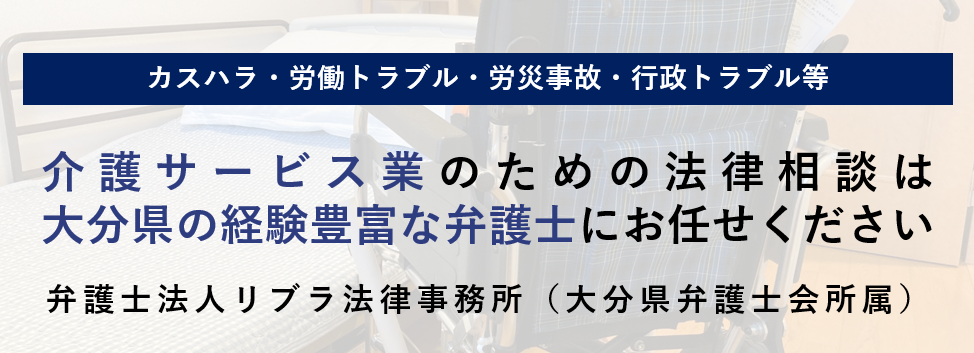介護施設でもカスハラが見られます。
様々な施設がこの問題に悩まされています。以下では、法的観点から、カスハラへの対応策を解説します。

介護施設におけるカスハラとは?
介護施設でのカスハラとは、利用者及びその家族が、職員に対して行うハラスメント(過剰な要求や理不尽な要求)をいいます。もはや社会問題化しているといってよいです。
カスハラへの対応を間違えると、職員を精神的に圧迫し、ひいては職場の雰囲気を悪化させるばかりか、ブログやSNSにより施設の悪評として拡散する可能性もあります。
このことは、介護施設でも例外ではありません。
厚生労働省は「職場のパワーハラスメント対策についての有識者検討会報告書」(2018年3月)で、はじめて顧客からのクレームに言及し、「顧客や取引先からの著しい迷惑行為は職場のパワーハラスメントと類似性がある」として「社会全体で機運を醸成していくことが必要」だとの意見も記載されています。
このことは、クレームが社会問題として認識されたといえるでしょう。
▼関連記事はこちらから▼
クレーム対応は弁護士に依頼すべき?弁護士に依頼するメリット・流れについて解説!
飲食店で起こるクレームへの対処法とは?-551のカスハラ事件について思うこと-
また、近年、介護制度を支えるケアマネージャーに対する「カスハラ(カスタマーハラスメント)」が深刻化しており、彼らの離職や心身の不調を招く一因となっています。
高齢者世代によるクレームも増加
日本では超高齢化社会を迎えたといわれ、一部では「シルバーモンスター」の存在も脅威として捉えられています。
「犯罪白書」(平成29年版)には、2016年の刑法犯検挙者のうち65歳以上の高齢者が、他の年齢層と比較して検挙者が最も多く、全体の20.8パーセントを占めた、とのことです。殊に、暴行で検挙された高齢者が増加しているとのことです。その原因は様々でしょうが、独居や身寄りが周囲にいないことでの疎外感や孤独感からくる怒りもあろうかと存じます。
介護施設では、利用者及び家族等による職員に対するハラスメントが、職員の確保を妨げる要因となっているとの認識から、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組みの例として、
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
②被害者への配慮のための取組み
③被害防止のための取組み
を規定する等して、介護現場におけるパワーハラスメントを防止することが求められています(介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について 等)。実際、「過労死等の労災補償状況・平成30年度(厚生労働省)」によると、精神障害の労災請求件数が1820件あるところ、請求件数のうち、業種別(大分類)のうち一番多いのが「医療・福祉」であり、業種別(中分類)では、大分類である「医療・福祉」のうち「社会保険・社会福祉・介護事業」が一番多いとされています(平成30年度「過労死等の労災補償状況」を公表します)
カスハラが起こる背景
多くの施設は、現在でも、顧客満足を最優先に考えています。ですが、現代社会はインターネットにより容易に大量の情報へのアクセスが可能であることから、同業他社との比較が容易になり、顧客の期待が増して同種のサービスを要求する、あるいは、施設への要求が奏功した事例を見た顧客が更に要求を行う、という状況もあろうかと存じます。
カスハラの具体例
1 欠陥があった商品・サービスの代金より高額な賠償を求める
介護施設では、提供されるサービスや物品について、利用者の期待と異なる事態が発生することがあります。しかし、その際にサービスの代金や物品の価格をはるかに超える賠償を求めるケースは、カスハラの一種と見なされます。
具体例:ある介護施設で、入居者の衣類を洗濯した際、誤って他の入居者のものと混じってしまい、紛失させてしまうという出来事がありました。施設側はすぐに謝罪し、新しい衣類を購入して弁償する旨を申し出ました。しかし、利用者のモンスター家族は「これは祖母が大切にしていた思い出の品だ。精神的苦痛を受けたので、衣類の代金の10倍にあたる30万円を賠償しろ。でなければ消費者センターに通報する」と主張し、執拗に高額な賠償を要求しました。施設側は丁寧な説明を繰り返しましたが、最終的には弁護士を交えて話し合う事態に発展しました。
2 サービスの質・量について執拗にクレームをつける
介護サービスは個別性が高く、利用者の状態やニーズによって最適なケアが異なります。そのため、サービスの質や量について利用者やそのモンスター家族から意見が出ることは当然ですが、それが過剰かつ執拗になるとカスハラとなります。
具体例:あるデイサービスでは、毎日利用する入居者のモンスター家族から、ほぼ日課のようにクレームの電話がかかってきました。「今日の入浴介助は雑だったのではないか」「レクリエーションの時間が短すぎる」「他の利用者に比べて、うちの祖父への声かけが少ない」など、日々の些細な出来事を指摘し、その都度改善を求めました。施設側は毎回真摯に話を聞き、状況を確認し、改善策を検討・実行しましたが、それでもクレームは止まりませんでした。しまいには、「うちの祖父の介護記録を毎日詳細に提出しろ。もし少しでも怠慢が見られたら、ただでは済まない」と、職員の業務に過度な負担をかける要求までエスカレートしていきました。
3 施設から精神的苦痛を与えられたとして慰謝料を求める
介護施設での生活においては、人間関係や些細なトラブルから、利用者や家族が精神的な不快感を抱くこともあります。しかし、その全てを「精神的苦痛を与えられた」として、慰謝料を求める行為はカスハラに該当する場合があります。
具体例:ある有料老人ホームの入居者が、他の入居者との些細な口論をきっかけに「この施設にいると精神的に追い詰められる。スタッフも見て見ぬふりをして、私を守ってくれなかった」と主張し始めました。施設側は双方の入居者から話を聞き、仲裁を試み、その後の見守りを強化するなどの対応を取りました。しかし、その入居者のモンスター家族は「施設側の管理不行き届きで、母は多大な精神的苦痛を被った。慰謝料として100万円を支払え。応じなければ、行政に訴える」と一方的に通告してきました。施設側は丁寧に状況を説明し、慰謝料支払いの根拠がないことを伝えましたが、家族は聞く耳を持たず、繰り返し慰謝料を要求しました。
4 職員の接客や言葉遣いにクレームを述べる
介護施設の職員は、多様な利用者や家族と接するため、言葉遣いや態度には細心の注意を払っています。しかし、一般的な範囲を超える過度な要求や、些細な言動を針小棒大に非難する行為はカスハラとなり得ます。
具体例:ある介護施設の新規入職職員が、利用者に対して「~ですよね?」と丁寧語で話したところ、その利用者のモンスター家族から「言葉遣いがなっていない!『~でございますか?』と言うべきだ!社会人としての常識がないのか!」と激しい口調でクレームが入りました。その家族はその後も、その職員の言葉遣いや表情、声のトーンまで細かく指摘し、他の職員と比較しては「あの職員は態度が悪いから、担当から外せ」と繰り返し要求しました。施設側が言葉遣いについて研修を行うなど改善を図っても、家族のクレームは収まらず、最終的にはその職員が精神的に疲弊し、退職を考えるまで追い込まれてしまいました。
5 苦情に対する対応が悪いとして更に苦情を述べる
利用者や家族からの苦情には、施設側は真摯に対応し、改善に努めるのが原則です。しかし、施設側の対応が不十分であると決めつけ、同じ内容や類似の苦情を繰り返し行い、対応そのものに不満を表明し続けることはカスハラに該当します。
具体例:ある介護施設で、入居者の居室のエアコンの調子が悪く、施設側が業者を手配して修理を行いました。しかし、修理後も利用者のモンスター家族から「修理が遅すぎる」「きちんと直っていないのではないか」「説明が不十分だ」といった苦情が続きました。施設側は状況を何度も確認し、追加の点検や説明を丁寧に行いましたが、家族は「対応が悪い」「誠意が見えない」と納得せず、最終的には「お前たちの対応の悪さで、うちの母は風邪を引いた!慰謝料を払え!」と、新たなクレームに発展させました。同じ内容の苦情を延々と繰り返し、対応のたびに新たな不満を述べるため、施設側は職員が疲弊する一方で、建設的な解決に至ることができませんでした。
6 自分だけの特別待遇を求め、あるいは気に入らない職員の解雇を求める
介護施設は、公平なサービス提供を原則としています。しかし、特定の利用者や家族が、他の利用者とは異なる特別扱いを要求したり、個人的な感情で職員の解雇を求める行為は、ハラスメントとして認識されます。
具体例:ある介護施設の入居者のモンスター家族が、施設に対して「うちの母には特別な食事を用意しろ。他の入居者と同じものは食べさせたくない」「夜間もつきっきりで職員を配置しろ」など、他の入居者には提供されていない、過剰な特別待遇を繰り返し要求しました。施設側が公平性の観点から断ると、その家族は「では、私が気に入らないあの職員をすぐにクビにしろ。あの職員がいる限り、母は快適に過ごせない」と、個人的な感情から特定の職員の解雇を要求しました。施設側は職員の評価は正当なプロセスで行われることを説明しましたが、家族は聞く耳を持たず、連日電話や面談で職員の解雇を迫り続け、職員が精神的に参ってしまう事態となりました。
7 施設側の些細な落ち度について謝罪文等の書面や土下座を要求する
介護現場では、どれほど注意を払っていても、些細なミスや行き違いが生じることはあります。しかし、その際に必要以上に高圧的な態度で、謝罪文の書面提出や土下座といった過度な謝罪を要求する行為は、職員の尊厳を著しく侵害するカスハラです。
具体例:ある介護施設で、職員が配薬をする際に、入居者の薬をトレイに乗せ忘れるという些細なミスがありました。すぐに別の職員が気付いて対応したため、入居者が薬を飲み忘れることはありませんでした。しかし、このことを知った入居者のモンスター家族は激怒し、施設を訪れるなり「うちの親を殺す気か!」「お前ら全員土下座しろ!」と大声で罵倒し始めました。さらに、「二度とこのようなことがないよう、謝罪文と再発防止策を明記した書面を今日中に提出しろ。でなければ、この件を行政に通報する」と要求し、職員が何時間も頭を下げることを強要しました。この出来事により、ミスをした職員だけでなく、その場に居合わせた他の職員も精神的なショックを受け、今後の業務に支障をきたすほどでした。
また、先ほど、ケアマネに対するカスハラが増加していると書きましたが、現実にも、下記のようなカスハラが生じています。
8 「俺は客だぞ!」暴言と無理難題のオンパレード
「お前らケアマネは俺たちの言うことを聞くのが仕事だろう!」「すぐに担当
を変えろ!でなければ本部に言ってやる!」
このような暴言を浴びせられるケースは後を絶ちません。サービス利用者や
モンスター家族の中には、「介護保険料を払っているのだから、ケアマネは自分の召使いのようなものだ」という誤った認識を持っている人もいます。
あるケアマネは、夜中に何度も電話をかけてきては、翌日すぐに対応できないような無理な要求を繰り返す利用者に悩まされていました。例えば、「今すぐ来て部屋の模様替えを手伝え」「来週の旅行の手配をしろ」といった、ケアマネの業務範囲を逸脱した要求です。断ると「誠意がない」「使えないケアマネだ」と罵倒され、精神的に追い詰められていきました。
9 性的嫌がらせ・つきまとい行為
カスハラは、言葉によるものだけではありません。性的な嫌がらせも深刻な問題です。
例えば、訪問時に不必要に体に触れようとする、性的な発言を繰り返す、プライベートな連絡先をしつこく聞いてくる、といったケースが報告されています。また、利用者のみならずそのモンスター家族から、事業所からの帰宅時に尾行される、自宅を特定しようとされるなど、つきまとい行為に発展することもあります。
あるケアマネは、担当利用者から「今度デートに行こう」「抱きしめてもいいか」などの誘いを執拗に受け、精神的な苦痛から担当を交代せざるを得なくなりました。しかし、交代後も別のケアマネに対して同様の行為が繰り返され、事業所全体で対応に苦慮しています。
10 土下座しろ!」「謝罪しろ!」執拗な謝罪要求と過度なクレーム
介護サービスにおいては、利用者の状況やニーズが多様であるため、時には行き違いや誤解が生じることもあります。しかし、その際に、利用者やモンスター家族から過度な謝罪を要求したり、些細なミスを針小棒大に非難したりするカスハラも増えています。
あるケースでは、ケアプランの説明が利用者の希望とわずかに異なっていたという理由で、利用者のモンスター家族から数時間にわたる説教を受け、「土下座して謝罪しろ」と強要されたケアマネがいました。その場で土下座を拒否したところ、後日、事業所に何度も抗議の電話をかけられ、最終的には行政にまで苦情を申し立てられました。結果としてケアマネは心身のバランスを崩し、休職を余儀なくされました。
「まさかうちが…」そのカスハラ、弁護士に任せませんか?
「うちの施設はアットホームだから大丈夫」「話し合えばわかるはず」。そう思っていませんか?しかし、残念ながら、介護現場でのカスタマーハラスメント(カスハラ)は、規模の大小にかかわらず、どんな施設にも忍び寄る深刻な問題です。
職員の疲弊、離職、そしてサービスの質の低下…。これらはすべて、放置されたカスハラが引き起こす悪循環です。そして何より、現場の職員に「なんとかしろ」と丸投げするのは、もはや時代遅れであり、職員を守る意識が低いと言わざるを得ません。
「うちのやり方」だけでは限界がある理由は次の通りです。
利用者やご家族からの正当なご意見には、真摯に耳を傾けるべきです。しかし、理不尽な要求や暴言、嫌がらせがエスカレートした場合、組織的な対応が必要です。
多くの介護事業所で、以下のような対応をされているかもしれません。
謝れば済む問題は謝る
「不快な思いをさせて申し訳ありません」
「手際が悪く申し訳ありません」
と、施設の落ち度ではない部分で頭を下げることで、その場を収める。
時間をかけて相手の言い分を聞く:
クレームが長引いても、ひたすら相手の要求を聞き出し、解決策を探ろう
と努力する。
複数人で対応にあたる:
一人で対応しきれない場合、他の職員や管理者が加わり、複数人で解決を
図る。
しかし、これらの「誠実な対応」が、かえってカスハラを助長してしまう
ケースが少なくありません。なぜなら、カスハラを行う側は「強く言えば要求が通る」「感情的に訴えれば得をする」と考えている場合があるからです。
なぜ、今すぐ「弁護士」が必要なのか?
介護事業者にとって、弁護士費用は決して安くはない、と感じるかもしれません。しかし、カスハラを放置する代償は、弁護士費用をはるかに上回ることをご存知でしょうか?
1 職員が守られる安心感
「何かあったら弁護士に任せられる」という安心感は、現場職員の精神的な負担を大きく軽減します。これは離職防止にも直結します。
2 早期解決による被害拡大の防止
悪質なカスハラは、放置すればするほどエスカレートし、事業所の評判や信頼を著しく損ねる可能性があります。弁護士が早期に関与することで、問題の長期化を防ぎ、被害を最小限に食い止めることができます。
3 毅然とした態度で臨める
弁護士という「組織外の第三者」が介入することで、カスハラを行う側は「これ以上は無理だ」と諦め、態度を軟化させることが少なくありません。弁護士は法律のプロとして、冷静かつ客観的に状況を判断し、適切な対応をアドバイスしてくれます。
4 不当な要求をはねつける盾
弁護士は、不当な要求に対して法的な根拠をもって反論し、毅然とした態度で臨むことができます。これにより、事業所が不必要な金銭的負担を負うことを防ぎます。
「警察に通報する」「弁護士に対応を任せる」。この言葉が、職員が安心して言える職場環境を構築することが、これからの介護経営には不可欠です。
また、弁護士に関与してもらう場合は、顧問弁護士として活用するのがお得です。
顧問弁護士は、何か問題が起きてから慌てるのではなく、日頃から法律の専門家が「かかりつけ医」のように事業所をサポートしてくれる制度です。カスハラだけでなく、労務問題や契約トラブルなど、様々な法律問題を早期に相談・解決でき、未然に防ぐことも可能です。これにより、職員は安心して業務に集中でき、経営者は本業に専念できるため、結果的に事業所の安定経営と成長に繋がります。トラブル時の高額な費用や時間的な負担を抑え、事業所の評判や信頼を守るため、まさに「守りの経営」に不可欠な存在です。
介護施設の事業主の皆様は、専門部署がなく「法的対応をどうしたらいいのか」というお悩みや、日々の業務遂行に忙しく、カスハラ対応に過剰な時間をかけられない、というお悩みをお持ちかと存じます。そんなとき、日常的に
付き合いのある顧問弁護士制度は、これらの悩みを解消することができます。
今すぐ、あなたの施設を守るために、ご連絡ください
「うちの施設は大丈夫」と過信せず、一度、弁護士に相談してみませんか?
たった一度の相談が、あなたの事業所を、そして大切な職員を守る大きな一歩となるはずです。
弁護士に相談するのは、よっぽど大変なことだと思っていませんか?
実は、もっと気軽に相談できます。例えば、利用者への対応で法律事務所に来るのが困難な場合でも、Web相談で皆様が介護施設に居ながら相談をして
いただくことも可能です。
連作先はこちらです
事務所名 弁護士法人リブラ法律事務所
大分市中島中央2-2-2
電話 097-538-7720
FAX 097-538-7730
URL:https://kigyo-lybralaw.com/
弁護士 井田雅貴(いだ まさき)
▼関連記事はこちらから▼
弁護士がクレーム対応やクレーマー対応をすることのメリットとは?
介護業におけるカスハラに関するまとめ
施設がカスハラ問題に取り組む際には、弁護士の支援を受けることが有効です。弁護士は以下のような方法で施設を支援します。
法的な助言
対策の策定
法的措置を執る
カスハラ問題に直面した際には、専門的な支援が必要となります。
また、弁護士であれば、問題となった事例を基に、事前のコンサルテーションやトレーニングを行い、カスハラを防止するための策を立てることも可能です。カスハラ問題に取り組むためには、まず弁護士にご相談ください。
Last Updated on 6月 11, 2025 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |